

特集『守れ〝幸せな映画〟』
ドラマの新しい頁をめくる時、
その陰に膨大な過去の歴史と物語が
控えていることを覚えていよう。
今年は戦後六十五年。
節目の夏に向かって
幾つかの催し物が企画されているようだ。
春が過ぎれば、
もうすぐ巡り来る「熊谷の夏」。
新年度を迎えて歩み始める
フレッシュマンに負けないように、
心して日々を過ごそう。
―編集後記より―
(各記事の紹介)
 深谷市の区画整理事業の一環で、 旧中仙道の道幅を広げるため、 『深谷シネマ』が移転する。  七ツ梅酒造跡 新天地〝旧七ツ梅酒造〟は築三百年で、 修復・維持が困難だった。  深谷シネマ館主・竹石研二さん 今も映画館の受付に立つ竹石さんは、お客さんと声を交わし合う。上映前にはスクリーンの前で、 ちょっと早口に恒例の挨拶をする。勿論映写もする。口癖は「わぁ、いいなあ」の感動直球型。 開館五周年の記念パーティでは、花束を抱いて男泣きに泣いた。この人が、深谷の街にどんな風を吹かせるのだろう。  受付風景  左・武重邦夫さん  平成20年10月13日 『七ツ梅』にて 左・中越信輔さん(〝いのちの作法〟助監督) 右・武重さん |
1頁―『浪漫的竹石イズム』 竹石さんにとって映画とはなんなのだろう。その鍵は少年時代にあった。 昭和二十三年、墨田区向島に生まれた竹石少年は毎日遅くまで原っぱで遊びまわっていた。当時は年齢の違う子ども達もみんな仲良く遊んだ。たき火をしたりけっこう悪さもして、今考えると危ないなあと思うが、大人は黙って見守ってくれていた。そんな無心な少年時代が自分の原点だと振り返る。 街大工で寡黙な父と優しい母、薪でご飯を炊いていた時代だ。六人兄弟で四人の男の子の一番下だった竹石さんはお使いに行く係。下町の商店街の肉屋へいかフライを買いに行くと、揚げているのを待つ間にポテトフライをくれる。仕事帰りに一杯飲み屋で塩豆をつまみに立ち飲みで一杯引っかける父が、月一回の給料日だけは店に上がり込んで飲む。その自転車を引き取りに迎えに行くのも少年の役目だった。味噌や醤油も計り売りで瓶を持って買いに行った。 商店街の人には本当にお世話になった。それが、今、商店街の中の「まちの映画館」としてあることにつながっている。あの頃の街並みは地図に書くこともできる。「故郷をふらりと歩き回って、みんなのことを映画を撮りたいなあ」と目を細める竹石さんだった。 小学生の頃から「押上シネマ」には子どもだけで歩いて出かけた。当時流行っていたのは、東映のチャンバラ映画三本だて。立ち見も当たり前のすし詰めの中、大人をかき分けて前へ行き、時にはステージに寝ころんでスクリーンをみつめた。伏見扇太郎、錦之助など、スターの居並ぶ日本映画全盛の時代だった。 『今村プロダクション』で、故今村昌平監督の右腕となり、また同時に、同監督が昭和五十年に立ち上げた『横浜映画放送専門学院(現日本映画学校)』創立メンバーの中心的な存在である武重邦夫さんが、『日刊ブログ新聞ぶらっと(平成十九年三月)』で、次のように書いている。 ……竹石さんはこの学院の第一期生であった…… 『初年度の僕のクラスは平均年齢が二十歳弱、一番の年長学生が二十七歳の竹石研二だった。竹石は清瀬から通ってきている学生で、既に結婚して子供もいた。僕が三十五歳で独身なのに、学生の竹石が所帯持ちなのは何か不当な気もしないでもなかったが、彼は落ち着いた誠実な学生だったので許せたのだが(笑) 「先生、カンパしてください」二ヶ月が過ぎた頃、ゼミ長が募金箱を持ってきた。 竹石さんに二番目の子供が生まれるのでクラスでカンパを集めているのだそうだ。 むむむ、学生の癖にまた子供など作りおって生意気な!……一瞬そう思ったが、「竹石さん、出産費用が払えないんですよ」と聞かされ思わず一万円札を渡した。』 『横浜の初期の学生は、日本映画の最衰退期で就職がなく様々な職業に散って行った。竹石研二は卒業後、日活の教育映画部に入り地方で教育映画を上映する仕事についた。やがて日活が潰れ、彼はしばらく生協に勤めていたが、五十歳を期して辞職した。 二十一世紀を迎えた頃、竹石は深谷市の銀行の廃ビルを借りて五十席の映画館を立ち上げた。常識では採算が合わない小さな劇場だったが、深谷市民がわが町の映画館として支え続けてくれた。 竹石研二の映画館は「深谷シネマ」として近辺の人々に愛されている。彼はこの小さな映画館を「チネ・フェリーチェ」と名付けた。イタリア語で「幸せな映画」という意味である。』 『二〇〇六年の九月、竹石は五月に亡くなった今村昌平監督の「にあんちゃん」の追悼上映を行った。僕もゲストとして招かれたが、下駄履きで気楽に集まってくる深谷の町の人々に、映画と映画館に対する温かい愛情を感じて嬉しく思った。 かつて、日本の映画館は地域の人々が集まるコミュニケーションの場所だった。そうした場を取り戻すのは不可能だと言われていたが、竹石研二は果敢に挑戦し成功させた。 今村さんの〝道なき荒野を目指せ!〟を、今、卒業生たちが継いでくれている。』 (抜萃編集部) ------------------------------------ 竹石さんはこのようにして、深谷シネマを作った。 その一途な思いに応えて、これまで何人もの映画監督が深谷へやって来た。小さな劇場のスクリーンの前で映画へのあつい思いを肉声で語りかけてくれた。 「まち」を元気にしたい。 映画はそのための一つのコマになるだろう。そんな理想を竹石さんは描いている。 映画館を通して新しく生まれるもの。そこに向かって前へ進み続けるのが、竹石さんの自己表現だ。 |
  『深谷シネマ』新しい映画館 〒366-0825 深谷市深谷町9-12 Tel:048-551-4592/Fax:048-551-4593 [HP] http://fukayacinema.jp [E-Mail] fc@fukayacinema.jp 座席数は60席(固定席57席、 車椅子席1席、親子室2席) スクリーンは最大5.8m×2.4m  建築家・清水潤一さん (「住まいとまち創り集団木犀」代表)  裏手から見る〝旧七ツ梅〟の佇い  壁焼き |
2頁―『江戸時代の造り酒屋を 現代に蘇らせた〝夢通う銀幕〟』 新『深谷シネマ』を設計した清水潤一さんにお話を伺ったのは二月中旬だった。 竹石さんとは第一シネマ創設以前からの知り合いだという。映画に賭ける夢をかたちにした竹石さんの横にはいつもこの人がいたのだ。 友情と共感 竹石さんとの出会いは、異業種交流会の七夕セミナーだった。その映画への一途な思いに共鳴した。 当時生協職員だった竹石さんが五十歳を期して退職、映画館を作ろうと、「県北にミニシアターを 市民の会」を発足させると、共に駅頭に立って、署名活動も繰り広げた。 その旗揚げ上映が十一年前の三月、井筒和幸監督の「のど自慢」だった。常設館獲得の道程は遠かった。 土地っ子ではない竹石さんを、地域の多くの人に引き合わせ、「まちの映画館をつくろう」と物心での支援を仰ぐために奔走した。 営業をやめた老舗『フクノヤ』の一部を映画館として開館できたのが、平成十三年のこと。オープニングの「愛染かつら」上映に近所のお年寄りたちも詰めかけ連日の賑わいとなった。 現在の地所「旧さくら銀行跡」で上映を始めたのはその翌年だった。以来、『深谷シネマ』の理事の一人として陣頭に立って来たことになる。 時と街への「意匠」 高校生の頃建築家を志したという清水さんの専門は、建築の中でも「意匠」。駅前の洋菓子店『シェ・オーサワ』や、『あゆみ作業所』などを手がけた。現在は、高齢者集合住宅の仕事に関わっている。 代表を務める『木犀』で深谷におけるまち創りの活動を始めたのは十年前のことだ。〝埼玉建築士会大里支部〟有志が集まる勉強会が母体となった。 仲間たちが最初に手がけたのは、街中の煉瓦造りの歴史的建造物の調査だった。 これが「七ツ梅酒造」の活用提案につながった。この建物の魅力を知り、それを生かして何ができるか、ワークショップを催し、継続して問い続けた。 一方、区画整理事業に伴う新シネマの構想は、三年前から検討されていた。 深谷駅近くの廃業した料理店など、幾つか移転候補地も二転三転し、会員で知恵を絞った。 だが、結局は予算との兼ね合いなどもあり、清水さんの個人案での施工が決定した。 渾身の日々 改築に際して最優先したのは、三百年前の堅牢な蔵をかたちを崩さないで蘇らせること。解体すると予想以上にいたみが酷い。使える物だけ使って土台はやり直した。 柱は杉、梁は松。ジャッキアップして持ち上げた江戸時代の骨組みの様子などは、シネマ移転を追いかけ続けた映画美学校の生徒達が映画製作のために記録に残した。 こんな仕事はもう今日の技術ではできない。屋根瓦も泥を置いてから瓦を張る昔ながらの工法、興が乗る現場だが、垂木などもボロボロだった。 蘇った建物にはロビーにその面影を残した。天井は低く張り変え、フロアや壁、シートなどは、撮影技師の永吉洋介さんに任せた。 思えば映画を見る間もなかったと清水さん。厳しい経済情勢の昨今、地域復興の核としてシネマを軌道に乗せるため「しばらく肩の荷が下りません」と静かに笑った。 壁焼き 深谷シネマの強力な助っ人、中島義明さんは、〝手づくりの竹とんぼ〟でお馴染み。ロケで深谷を訪れた俳優さん達に贈る竹とんぼでマスコミも賑わす映画狂だ。 小雪降る二月十三日、「歓喜の歌」ロケの行われた『中島建設』で、新劇場に使われる外壁材の焼き込み加工が行われた。この日は呼びかけに応じた数人のボランティアが参加。新劇場の建て込みに当たって、シネマを支援する気持ちをこめての作業となった。 清水さんや中島さんをお手本 にガスバーナーを用いて杉板を黒く焼き、その後ワイヤーブラシでこすり取って綺麗にする。 裏には自分の名前をサインする。少しでも自分の手で、応援の気持ちを表そうと参加したファンたち。この板が建物の外壁、つまり「顔」になるのだ。 雪の中、映画美学校のグループも撮影に訪れた。市民参加の映画館作りを追いかける映画青年達は真剣にカメラをまわしていた。旧映画館のようすなども含めて一本のドキュメンタリーにまとめられる予定だ。 |
 菊川慶子さん 2月6日 生活クラブ生協熊谷センター  映画『六ヶ所村ラプソディー』 平成十八年作品。  深谷シネマゲストトーク 鎌仲ひとみ監督 鎌仲監督は生活者の感覚を大切に映画に携わってきた。出産・子育て中の大変な時期に自分の足元、下町の暮らしを撮ったことでアイデンティを取り戻したという。その後「ヒバクシャ」製作。現在、「ミツバチの羽音と地球の回転」が製作最終段階に入っている。  『生活クラブ生協・ワーカーズつくし』 『生活クラブ生協』には組合員活動の一つとして「六カ所委員会」があり、小川町での上映会や署名運動を行っている。  「ドキュメンタリー自主上映会」 |
3 頁―『もっと知ろうよ核燃サイクル』 映画『六ヶ所村ラプソディー』菊川慶子さん講演 『深谷シネマ』での上映会は平成十九年六月。 六ヶ所村核燃料再処理施設の問題を周辺に暮らす住民達の生活や背景、思いを交えつつ構成した記録映画。反対・賛成・中立派を取材している。若い人達による自主上映会が各地で開かれた。 菊川さんは、『深谷シネマ』で行ってきた〈ドキュメンタリー自主上映会〉で取り組んだ『六ヶ所村ラプソディー』の主たる登場人物だ。 「原子力発電」の問題は難しい。新聞記事などを読んでも右から左へ抜けてしまう。ところがスクリーンの中に広がった畑と土仕事している菊川さんの姿――映画を見ると、今《六ヶ所村》で何が起きているか、それがどんなに怖いことか、慄然とする。放射能が海を汚しても、大気を汚しても、それは見えない。 その見えない〈放射能の危険〉に対して、村で反対運動をしている菊川さんは、農家として地元に暮らす婦人だった。若者たちと街頭でビラを配り、抗議に出かける姿に襟を正す思いだ。 菊川さんは小柄で物静かな方だが、講演に入ると言葉は淀みなく志の強さが窺えた。 六ヶ所村は「核燃城下町」、給付金や「日本原燃」が丸抱えする施設などによって〝日本一お金持ちの村〟として潤い、反対運動も押さえ込まれてしまった。 そんな中に暮らして「チューリップまつり」やハーブ畑で収益を生み、NPO組織も立ち上げた菊川さん。その生い立ちは、村を十五歳で就職と同時に離れ、長く都内に暮らした。市民運動の経験も全くなし。 それが「チェルノブイリの事故」をきっかけに立ち上がった。家族を説き伏せてUターンを決行したのは二十年前。子どもの頃は大嫌いだった農業で食べていく道を選んだ。 思いだけで反対運動に入り、機動隊と向き合うデモなどでは足が震えた。当時の町長は選挙で「凍結」を謳っていた。漁師も漁船を出して「核のゴミ捨て」に来る船の寄港を阻止、婦人連が座り込みをするなど、反対運動が盛んだった。 それが現在では生活のために圧力に屈し、切り崩されてしまったことの無念。長い間に目の前に既成事実が積み上げられていった。そして、我が子が活動に距離をおくようになってしまったことにも触れて、「子どもたちに迷惑をかけすぎたかな」の言葉が重かった。 だが、菊川さんは雇用創出のためにルバーブジャムを開発したり、両親の働いていた牛舎を改造したゲストハウスで「自然へ出る学校」を開いたりと、更に展望を深めている。 「どうしてここへ飛び込んで来たのか? そのエネルギーはどこからきているのか?」と尋ねると、話は親の世代の戦争責任に繋がった。 樺太に暮らしていた両親は敗戦で無一文となって引き揚げ、六カ所村に入植。その時菊川さんは三歳だった。親に対して「なぜ戦争に反対しなかったのか」と問い詰めていた自分だから、「チェルノブイリ」の際、同じ地球上で起こっていることを黙って見過ごすことができなかった。こんなことは歴史上になかったこと。彼の地の幼子の姿が我が子に重なったという。 今では殆どの村人が関連産業で働いている。再処理工場のすぐ前には学校給食センター。一大国家プロジェクトに対して世界中から視察者がやって来る。 だが、ここはもともと土が良くて農業に適している。東京・大阪の食糧自給率四%に対して、青森では百二十%。これを放射能で汚していいのか。〝放射能感受性〟は小さい子ほど高く、赤ちゃんは大人の四倍。私たちは子どもを守らなければならない。そして〈汚染された食料を引き受ける覚悟があるのか〉――一人一人が問われている。 菊川さんは現在執筆中。本ができたら国会議員に働きかけたいという。また、映画が公開されてあちこちで動きが生まれたことを心強いと語った。 -------------------------------- 「ドキュメンタリー自主上映会」 『深谷シネマ』での上映会は平成十九年六月のことだった。記録映画の好きな仲間達がはじめて自主上映に取り組んだのはその一年前。自分たちの暮らす街で夜間中学の記録「こんばんは」を観ようという有志が集った。その後取り組んだ作品は「水になった村」「ひめゆり」ほか。 メンバーは会社員、整体師、劇団員など。 |
 しばらくは花の上なる月夜哉 ばせを 芭蕉句碑(通称花塚) 我も其阿弥陀笠きて 咲く花に うしろハ見せぬ熊谷さくら 三陀羅法師狂歌碑(文化五年)  横田さんと住職   乳(ち)の留め金のデザインが熊谷桜   石上寺のそばの高い建物から |
4頁―石上寺平成絵巻その8 『幻の桜が無事ご帰還』 三年前から始まった〝本堂再建〟は北条堤名残の土手、植栽を残すのみとなった。 本堂中央には御影石の須弥壇が設えられた。岡安住職が尊び、それを模した唐招提寺を初め、天平の頃のものは石造りであったことによる。 安置される本尊・千手観音は京都の仏師松本明慶師の工房で製作中。これから旧本堂の修復にかかるため、落慶式は来年になる運びだ。 熊谷桜発祥の地 二月十五日、江戸期からの桜の名所に〝熊谷桜〟が無事戻った。もとは鐘楼後方にあった八本の桜たち。再建工事が始まる前に『久保造園(佐谷田)』に避難させ、大切に守り育てられていた。 この桜は平成六年に『桜ファンクラブ(主宰横田透)』に寄贈されたもの。 その後〝熊谷桜発祥の地・石上寺〟のシンボルとして親しまれていた。今では各地に移植されているが、やはりその由来、纏まった数、姿形からいってここがベストポジション。 その移植時、鐘楼再建の際には、あやかって図案化した瓦の桜模様が間違っており、工事直前に焼き直された。長く幻の桜として謎の多かった〝熊谷桜〟の正体が突きとめられたばかりだったからだ。 〝熊谷桜〟は、淡いピンクの小輪が下向きに咲く八重の花で長い二本の雌しべが特徴だ。 今日、石段下に移された灯籠に飾られている図案は桜と「揚げ羽の蝶」の寺紋で北条攻めに纏わる縁起を伝えているが、こちらは一重。〝熊谷桜〟の姿が確定できなかった頃の建立ということになる。 今回の本堂再建では奈良の『山本瓦工業』で焼いた屋根瓦、そして正面扉に打ち込まれた金具・乳(ち)の留め金のデザインが熊谷桜となっている。 図案は絵心のある住職が描き、その長い雌しべは、直実公の「甲の鍬形」を意図した。 更に観音開きのガラス内戸の飾り窓も桜のかたちだ。丸窓の予定を変更しての住職の こだわり。 「あと三年もすれば新しい桜の名所になりますよ」と嬉しそうな桜守・横田さん(本業は染色家)であった。 この日の移植は、時期的にはぎりぎりセーフ。この寒い時期でも花芽は既に開花の準備を始めている。三月中旬に他の桜に先駆けて咲く〝熊谷桜。 「木は根っこさえしっかりしていれば大丈夫、今年も健気に咲いてくれるはずです」と横田さんは住職と話し込んでいた。 木花咲耶姫 そこへ、旧知の人形作家・持田澄枝さんが「よかったですね」と駆け寄ってきた。これまでも工事の様子を窺っていたのだという。 そして、岡安住職の口からは、本堂に持田さん製作による「木花咲耶姫(このはなさくやひめ)」の人形を飾るという話が飛び出した。 この有名な神話の世界のお姫さまには幾通りかの物語が伝えられ、持田さんは目下イメージを膨らましている最中ということだ。 「木花咲耶姫」は、かつて屋久島の詩人・故山尾三省も口にしていた…… 〝花を咲かせる〟ことを国造りに重ねた古代のお伽話には深い命の思想が示唆されている。その姫が如何なる人形となって蘇るのだろう。 この日はまた、石上寺のそばのマンションから写真を撮ることもできた。 ベランダの真正面がお寺という絶好の場所。夕日が左右の黄金の鴟尾の間に落ちる様は本当に見事だそうだ。 春になれば桜が咲き、人それぞれ花に託した夢を重ねる。移植を見守りながら、人の思い花の心根を噛みしめた。眼前にさきがけの桜、歴史の幻が立ちのぼった。 ○追記 (三月十三日、一番日当たりのいい枝の熊谷桜が綻び始めているのを確認できた。) |
  『熊谷サティ』より少し下り、国道十七号より一本線路側に奥まった界隈、ここは〝憲兵隊通り〟と呼び習わされてきた。この通りにはかつて煎餅屋・寿司屋・納豆屋・肉屋・畳屋・洋服店・魚屋・豆腐屋・米屋・石屋・クリーニング屋・下駄屋が軒を連ね、ちんどんやも回ってきた。 この生活道路に今も威勢のいい呼び声と通りがかりの人たちの挨拶が飛び交う、人情味溢れる八百屋『いのうえストアー』がある。  井上豊吉さん定子さん  大葉を詰める豊吉さん  野菜果物の色合いが路上へ溢れる |
5頁―『街の八百屋 いのうえストアー』 心通う路 「いらっしゃい、安いよ、安いよ」「エーッ、いちご、いちご」 通りに親しみ深い声が響き渡る。向かいの喫茶店に来たついでに立ち寄るというお客さんも多い。下校時には学童が「ただいま」……すかさず「おかえりなさい」の声が返る。 店頭には野菜や果物がずらりと並んでいるが、ただ単に〝買う〟だけでないみんなの心の通い路なのだ。 八百屋三代 鴻巣の出で三代続く八百屋を切り盛りするのは、井上三兄弟とその奥さん達。昭和十年生まれの豊吉さんが跡を取ったのは二十五歳の頃だ。 以来半世紀の歴史をぽつぽつと語りながら豊吉さんは、片時も手を休めない。 「無駄が出ないように考えるんだよ」。これから配達に行く居酒屋のために大葉を一枚一枚綺麗に揃えてゴムでとめる。あるいは根生姜の大株を切り分け、きんぴらごぼう用にゴボウと人参を刻み、使い勝手がいいように心を尽くす。 戸外での水仕事に手が凍えると、焚き火に手をかざしてはまたすぐ作業に戻り、時間になると自転車に乗って配達に回る。保育園の給食や学校の調理実習にも長年野菜を調達してきた。 豊吉さんの下には和男、哲男さん。家族の他にも最盛期にはパート、子守りさんを抱えていた。 年季奉公 跡取りの豊吉さんは上野の昭和通りにあった店で修業した。そこは魚も扱っていて、「符丁(商店で値段をつけるために使われる隠語)」を覚えるためだった。 戻ってからは家で見習い修業。当時の市場は今の東京ガスのところにあった。父親は口数が少なく叱られたこともなかったという。 昔は大きなトラックで荷を運んだ。朝六時に男達が出かけて行き、戻ってくると女たちの出番。何とか算段して並べきる。 手書きの売出しチラシは倉庫にある印刷機で今も刷る。天井からは時代を経た案内看板などが吊り下がり、乳製品やパン、魚介類や菓子、雑貨など一通りのものが揃う。自家製沢庵、国産大豆、ずいきもあった。 かつては隣の空き地を畑にして牛蒡や人参を埋けておいたそうだ。 共に稼ぐ 口数の少ない男衆に変わって四方山話をあれこれ言い足してくれたのは、定子さんと幾江さん。……朝から晩まで立ち通し、レジ前には行列が絶えなかった。昼ご飯もおちおち食べる間もなく、毎日追い立てられるようだった。 大晦日まで働き詰めで「紅白歌合戦」は集金の車の中で聞いた。「暮れには白菜を三百把配達したよ」と、哲男さん。貴重品のバナナは房では扱えず、一本ずつ切って売ったという。親父に怒られたのはほうれん草を寝かせておいた時と教えてくれた。 時は移りて 今は「人が空っぽ」、ここに暮らしていた人も代変わりして余所へ移り、お客は昔からのご贔屓さんばかり。跡継ぎもいないし、自分たちも高齢化でいつまで店をあけていられるか心許ないと言いながら、どうしてどうして、元気いっぱいのみなさん。街の八百屋が姿を消していく中で、野菜を食べているお陰か全員健康で有り難いと笑う。 さあ、よってらしゃい この店は暮らしの知恵もいっぱいだ。この間おいしかった小粒苺がないので尋ねると、「今日は給料日だから高い苺しかないんだよ」。 いいゴボウがあるのに見とれていると、「節分には鰯を焼いてけんちん汁を作るもんだ」。去年覚えたのは、「お彼岸が来たらアサリが出る」ことだった。 近くの病院に療養中の人たちが気安く立ち寄れる店でもある。他愛ない世間話に興じたり、トマトなどを切って食べるスペースを作ったり、さりげなく見守って小さなコミュニティとなっている。表には地域の「子ども百十番」の札も掲げられている。 これが当たり前! 人情飛び交うわが町自慢の八百屋をいつまでも大切にしたい。 |
 桜写真 行田・丸墓山 茶封筒の中から出された何枚もの写真が机の上に並べられた。ぼーうっと淡く霞む桜、桜、桜。立春を過ぎて小雪まじりの日々が続いた二月のある日、幻想的な花の写真の数々に目を見張った。ところは『くまがや館』写真教室、講師を務めるのは西田昌稔さんだ。  桜写真 秩父・長泉院「よみがえりの一本桜」 西田さんがこれま で撮ってきた桜の 写真は、全盛期の 清雲寺のしだれ桜 や森林公園、二本 木峠、元荒川、忍 城など。建物を背 景にしたり、水を 配したり、あるい は花のアップ、落 花の風情とアング ルもさまざまだ。   生きる技 「桜を撮るのであれば、こんな方法・場所・構図がありますよ」と、自らの作品をモデルに説明をしている西田昌稔さん。この写真教室で教えるようになって〝カルチャーセラピー〟ということを実感したという。 何かに励むことで弱くなっていた体や心の力が蘇ることの不思議。そのお手伝いをすることは、自分がこれまで生きてこられたことへの恩返しと、他にも幾つかの写真サークルの立ち上げから関わっている。 生徒さんの写真を評しながら「自己主張のある作品」、「あなたの個性が出ている写真」という言葉が続く。 「どこがいいのか」「どれが好きなのか」、考えさせながらそれぞれの力を伸ばす。トリミングや焼き方で写真が変わることをパソコン画面で示しながらの講義だった。 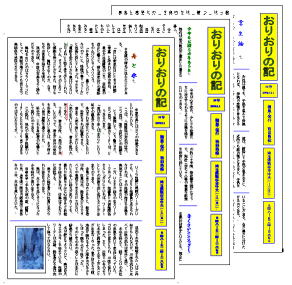 『おりおりの記』  「埼玉・群馬の花の写真なら西田さん」と。  自宅にて |
6頁/7頁―まちを彩るひとびと その13 『おりおりの花の写し』 通信発行 西田さんが五年前から定期発行している写真付きの通信誌が『おりおりの記』である。文字通り時節時節に届く本誌はテーマも様々、写真は清々しく、引用される書物なども多岐にわたり、平素見過ごしがちな風土事物を切り取って見事である。 この時代、写真を撮る人、ブログなどで文章を発信する人はたくさんいる。が、西田さんの写真や文章の魅力は、奥の深い真っ直ぐな世界観に立っていること、それを支える〝目の力〟が感じられるこ とだ。 人生の自覚 かつての西田さんは、第一線に立って国内各地を回る企業戦士だった。 『日本たばこ産業』という会社の中で経営合理化・組織や人員整理など、体を張って激務に当たる日々。派閥に入らなかった西田さんは職務に専心することで部長職まで登りつめた。 組織を支えるのは〝エリート〟よりその後で砂埃を浴びている〝二番手〟〝三番手〟というのが持論。 自分を「僕はタイプとしては鈍、人の倍努力しないと駄目なんです」と評する。弱い側の痛みも受け止めて、役を全うしたら早々に退こうと決めていた。 花の写真 第二の人生を見越して、五十歳を過ぎて始めたのが、〝写真〟だった。 もともと山が好きだった。若き日の山行きにはカメラを携えて、シラネアオイなど好きな高山植物などを撮っていた。 先輩に誘われて参加したのが「二科会写真部研究会」、そこで写真家・秋山庄太郎と出会う。西田さんは師の花の写真に憧れた。 「何かモチーフを絞り込んだ方が上達が早いよ」と忠告されて以来、「花の写真」一筋。これをライフワークとして二科展で三回入選を果たした。 初受賞作は両神山の節分草。その時、記念に師が書いてくれた色紙には、「花開いて風雪多し」の言葉があった。 遺れるもの やがて、その写真人生も転機を迎える。 折節で大きく道を展開できたことを回顧する西田さんは「私は人に恵まれました」と言う。 「コンテストに出品してもそれは遺らないよ」と助言をしてくれた人がいた。それが写真家・花の紀行文作家大貫茂さんだった。初めて出した本『関東周辺花の名所撮影ガイド(山と渓谷社・平成八年)』の共著者である。 時に六十四歳、それからは本を作ることに専念した。 不思議なもので、一つ本を出すと次々に声が掛かる。「埼玉・群馬の花の写真なら西田さん」と信頼されて、出版社からの依頼が続いた。花、しかもこの周辺に絞って系統的にデータを揃え、撮影を重ねていたのが強みとなった。今では著書は二十冊余り、デジタルカメラ撮影、データ整理もこなしている。 カメラ・アイより そんな西田さんは決して偉ぶらない。それは写真にも現れる。「僕は野の花が好きです」「白い花が多いと言われますね」。 確かに主宰する「とんぼの会」などの展覧会場で目にしてきた作品は殆どが清楚な淡い色が基調だった。 「いかに美しく詩のある花を撮るか」、自分の目指す作風をよく考えて無駄録りはしない。きっちりロケハンをした上で、虚心坦懐に花に向き合うのが西田流だ。 無用なシャッターは押さない。更に二年前に俳句を始めると「俳画」に学んで、常とう的な表現でなくて「匂い付け」のような微妙な叙情を湛えた写真を目指すようになった。 赤々と渓一筋や山紅葉 秋風の吹き抜く町の工場かな 投稿している句誌『冬野』に掲載された俳句はていねいにファイルされていた。来年になったら写真と俳句で個展を開きたいと考えているという。 毎年『おりおりの記』新年号には新しい年への夢や抱負が綴られている。幾つになっても衰えない好奇心、感動できる感性こそが、得難い才能なのだろう。 ナズナの誘い 取材時冒頭、「どうして花の写真を撮るようになったのか」という問いに答えて、「僕の原点は、病床で眺めていたナズナ」と西田さんは答えた。 戦後間もない頃、結核は死に至る病だった。大学までバレーボール選手をしていた偉丈夫が一転、病に倒れた。一年間の寝たきり生活の中で、心励ましてくれたのが窓から見えたナズナ…… 「これで死んじゃいけない」 と頑張れた。その思いをずっと持ち続けられたことが、作品の美しさに表れている。 スポーツも仕事も同じで、能力の高い人というより、勘が良くて臨機応変に動ける人が力を発揮するのだそうだ。 〝気づける人〟ということだろうか。全体の流れが見えることが大事。そして、そこにはその人の生い立ちが出てくる。ピンチを救えるのはそんな人だ。だから、バレーをやっていても西田さんはそういう先輩に憧れ、後に続いてここまできた。 話を聞くうち、九人制バレーのアタッカーとして活躍した西田さんの面影が背後に立ち上がっていた。 この街にて 部屋に飾ってあった写真は、ソフトフォーカスの節分草、鷺草、長岡の花火…… 建築家の息子さんが設計した家の自室の壁は、薄いクリームとスカイブルーの色のペンキが施されていた。透明感のある西田さんの写真が際だっている。部屋にはパソコンと周辺機器、数々のカメラ、花の写真集以外にも様々な書籍が並んでいた。 お宅を辞去する際、前の空き地の、雑木林に目がいった。野趣に富んで、雪を被った姿がなんとも美しい。 足を停めていると、はじめは何もなかったのに、鳥が種を運んで来てここまで大きく群れ育ったのだという。 続けて、「この木は何か分かりますか」と教えて下さったのが野ばら。こんなところにあるのは珍しいことだそうだ。 部屋の窓からも見えたこの景色。この街で、こんなふうに日々を暮らすことの出来る西田さんの姿に、生きることの意味をみた。 ○西田さんは、写真教室の講師だけではなく、『くまがや館』主催の「チャリティ事業の実行委員長」・「うちわ祭り写真コンテストの実行委員長」もこなす。その姿勢にこそ教えられるもの大だ。 *『くまがや館』 埼玉県熊谷市筑波1-29 電 話 048-521-4625 FAX 048-521-4636 URL:http://www.kumagayakan.net/index.html |
 街中の小さな通り  梅薫る西覚寺  瑠璃光寺五重塔  『人は流転し……』  坂を登り、見下ろした塔  『ザビエル記念聖堂』 |
8頁―わたしの山口その2 『西の京再び・光の塔』 この小さな町は歩いてこそ心に馴染む。街中の小さな通りには「堅小路・錦小路」など古名が残り、木造の民家が手入れの行き届いた木肌を見せている。 一方で、二車線の緑濃い幹線道路〝パーク・ロード〟には県庁・美術館などが立ち並ぶ。「日本の道百選」に選ばれ、さすがに歴代の首相を生んだお国柄が偲ばれる。 維新の町 山口は二本の川に挟まれ、前に迫る山並みの地勢が京都に似るため、〝西の京〟と呼ばれる。大内氏が贅を尽くした古都は、一度下克上の時代に炎上するが、再び幕末となって「維新の町」として歴史の表舞台に立つ。狭い土地にそれらのスポットが点在している上〝日本一人口の少ない県庁所在地〟という静けさ。 山口駅などは木造平屋の駅舎で、なんとも愛らしい。そこから数駅、新幹線の停まる新山口駅ともなると駅前にホテルが林立し、ロータリーに「山頭火」の立像がある。白狐伝説が残る「湯田温泉」を愛した自由律俳句の漂泊の詩人は「風来居」に暮らした。 宇部空港からバス・電車を乗り継ぎ、旅のスタートは湯田温泉。駅に降り立つと、民家の軒先には梅、風花が舞っていた。山頭火の句碑が遺る湯の町をそぞろ歩きした。 中原中也の好んだ外郎(ういろう)を買い求め、ママが一人で切り盛りする飲み屋のカウンターで腹ごしらえ、それから温泉に入った。 七福神に因んだ露天の壺湯に全身浸かって願をかけ、さて、循環バスに飛び乗って市街へ。「西京橋」はすぐそこだ。 寺町に小雨が降る。父の眠る寺の門から紅梅の老木の枝が覗いていた。ヒマラヤユキノシタ、南天…… 母は墓前に、家から持参した水仙を生けた。薄闇に時雨れていく小路の先に山波が濃くなっていった。 夜は、ささやかな祝宴に河豚を食した。初老の夫婦が営む割烹は中心アーケード街の中。旅公演に訪れた宇野重吉の認めた〝めだかの学校〟の色紙がいい。 藍色の河豚をかたどった瀬戸物の皿に白く咲く河豚刺しは、恐る恐る尋ねると、手の届く値だった。初めての息子との乾杯だ。 瑠璃光寺五重塔 二日目、地図を片手に万作や梅の咲く龍福寺を経て、漸く「瑠璃光寺」に行き着いた。 その五重塔の木肌と木組み、そりの堅牢さ、美しさ。去年はじめて訪れた後に、久木綾子著『見残しの塔 周防国五重塔縁起』(新宿書房)を読み、再訪を期した。 父の遺した古い写真やスクラップ記事に加え、母に教えられたのが、八十九歳の女流作家のデビュー作。構想十四年、執筆四年だという。 『人は流転し、消え失せ、跡に塔が残った。 塔の名を、「瑠璃光寺五重塔」という。室町中期、寺は香積寺と号した。守護大名大内氏一族の興亡の歴史を秘めた国宝の塔である。歳月が塔の朱を洗い流し、素木に還し、古色を加えたが、美形は変わらない。 塔は、今日も中空にのびのびと五枚の翼を重ね、上昇の姿勢を保ちつづける。』冒頭より この日は、梅の花を前景にした光の春の佇まいが残像となって心を焦がした。境内裏の金比羅神社後方まで狭い急坂を登り、見下ろした塔の姿もよかった。 宮大工の家に住み込んだ他、郷土史家、建築家、中世史学者のもとでさまざまな資料を読み解いた末に日向、周防、若狭とつなげた一大絵巻をものにした作家のことが、再び胸に迫った。そのように生きることが出来るのだ。――そしてまたこの人、ザビエルも執念の人だ。 神の塔 山口のもう一つのシンボル、『ザビエル記念聖堂』は残念なことに漏電で平成三年に焼けてしまったが、市民の祈りの力によって再建された。 曲がりくねった坂道を登りつめたところに姿を現した三角錐の御堂は、光を背に白く輝いていた。 礼拝堂前面は斬新なステンドグラス。その「神の言葉」の図案の中にあった拳は力に満ちていた。輝き渡る御堂に荘重なパイプオルガンの音が鳴り響き、思わず跪く。聖書を開くと、ちょうど「キリストは復活した」の箇所だ。 二十年前、幼かった娘や両親と旧聖堂を訪れた。祈りつつ零れた涙の彼方に、おぼろげな未来が仄見える。 帰途、機上から飽かず地上を眺めた。 雲また雲の波だ。 着陸寸前、ここにもまた、薄闇の街に灯りが広がっていった。 (M・F) |
| /チャンプより 「子どもの話―絵本」植田邦弘さん 今回は、小学部一年生の子供たちが大好きな絵本を紹介します。 まず『おおきなかぶ―ロシアの昔話A・トルストイ再話』内田莉莎子訳・佐藤忠良画(福音館)、昔からある絵本ですが、昔に作られて、今も残っているものは、何かしらの良さがあるのだと思います。覚えやすい内容と繰り返しのリズム。最後の落ちの分かりやすさ。劇遊びをするときにもよく使います。 続いては、『わたしのワンピース』作・西巻茅子(こぐま社)、この本も昔からあるので、懐かしいと思った人も多いと思います。きれいなお話で、読むととってもテンションが上がります。 『はらぺこあおむし―作・絵エリック・カール』訳・もりひさし(偕成社)も定番です。いまでは珍しくない仕掛け絵本ですが、この本が作られたころは斬新だったそうです。この本の色使いがだいすきです。とってもワクワクさせてくれる絵本です。 次は作家の紹介です。「かがくいひろし(昭和三十年東京生まれ。平成十七年、『おもちのきもち―講談社絵本新人賞』で絵本作家として出発)」さんです。特別支援学校の教員をやっていたせいか、子供の心をがしっと捕まえます。ストーリーの意外性とおちが大好きです。代表作として、『おしくら・まんじゅう』『おふとんかけたら』『だるまさんが』(ブロンズ新社)『はっきよい畑場所』(講談社)などがあります。 読み聞かせを行う上で大切なことは、まずその絵本を読み手がおもしろいと思っているか。絵本のメッセージを受け取りつつ、それを子供に押し付けないこと。主役は子ども。受け取るか受け取らないかはその子の感受性がきめること。 また、一回読んだだけですぐに食いついてくる場合もあれば、じわじわ食いついてくる場合もあります。自分が面白いと感じたら、伝わるまで読み深める。 絵本は子供だけでなく、大人にとっても、とってもいいものです。絵本の中には普段の生活では触れることのできない世界があります。そんな世界に触れ、自分の感性を磨き、想像力を豊かにしてくれます。 私の絵本の楽しみ方を紹介します。宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』。私もとっても大好きなお話です。読みながら宇宙のことや色々なことを空想しました。この作品が絵本でも出版されています。『銀河鉄道の夜』影絵と文・藤城清治(講談社)です。この絵本を読んでから、また原作をよむと、さらにイメージ豊かに深く空想することができました。 最後に、大人が読んでもおもしろい絵本を紹介します。『はるにれ』作・絵姉崎一馬(福音館)『オレゴンの旅―作・ラスカル絵・ルイ・ジョス』訳・山田兼士(セーラー出版)『おじいちゃんがおばけになったわけ―作キム・フォップス・オーカソン絵・エヴァ・エリクソン』訳・菱木晃子(あすなろ書房)『おまえうまそうだな』作・絵宮西達也(ポプラ社) そして、『ホームランを打ったことのない君に』作・絵長谷川集平(理論社)『ゆきのひ―作・絵エズラ・ジャック・キーツ』訳・木島始(偕成社)……などがおすすめです。 |
9頁―『出会いから生まれた 若者達の連載メッセージ』 沖縄便り 「ムーチー(鬼餅)」湧田武司さん 沖縄では、旧暦の十二月八日に、「ムーチー」を食べる習慣があります。 「ムーチー」とは、沖縄では結構ポピュラーなお菓子で、餅粉をこね、砂糖で味付けを行い、月桃の葉で包んで蒸したものを言います。味も香りも良く、沖縄では老若男女問わず好まれるお菓子の一つです。 おいしいお菓子で、年中コンスタントに食されるお菓子なのですが、特に旧暦の十二月八日には沖縄全島で、その「ムーチー」が出回り、沢山の沖縄県民が「ムーチー」を食します。 では、何故旧暦のこの日に食べる習慣がついたのかと言うと、その由来は、沖縄県に伝わる昔話にあると言われています。 その昔話はどのようなものか、というと、その昔、沖縄に兄妹がおり、姉妹が転居した先で、兄が、家畜や人間を食す鬼になってしまったという話です。 人々を恐怖に陥れる鬼になった兄をどうにかする為、妹が取った行動は、鬼(兄)を退治するという事です。 妹は「ムーチー」を自分用のふつうの「ムーチー」と、鬼にも噛み切れないような〝鉄入りのムーチー〟を作りました。妹は鬼(兄)を崖まで連れて行き、わざと着物をはだけさせ、「ムーチー」を一緒に食べました。 妹は普通の餠を食べます。鬼(兄)は噛み切れず困っている「ムーチー」を平気で食べている妹に何故こんな〝堅いムーチー〟を食せるのか、そして妹のはだけた隙間からみえた陰部をみて、その口は何だと尋ねました。 妹は、「ムーチーを食べているのはこの口、そして下の口は鬼を食べる口ですよ」と答えました。 びっくりした鬼(兄)は、崖に誤って落ちて死んでしまいました。 その鬼(兄)が退治された日が旧暦の十二月八日であった事から、厄払いや、縁起物の意で「ムーチー」を旧暦のこの日に食べる習慣がついたと言われています。 沖縄では、「ムーチー」を食べる頃にかなり冷え込む事から、その時期を、〝ムーチービーサー〟と呼んでいます。 ――人は誰でも、この物語の(妹)に、そして兄(鬼)にもなり得るのかもしれません。何かに囚われ、その何かを成し遂げる事で、その本質を忘れていませんか? 自分はこれでいいのか、そして、どうしなければならないのか、常に考え行動しなさい…… 私は、この物語からそう教えられました。 今年の沖縄県の〝ムーチービーサー〟は、冷え込みました。「ムーチー」を食べながら鼻水を垂らしていた事を覚えています。 私達が当たり前と感じ、過ごしている行事には、様々な意味が込められています。先哲の残していった様々な意味を、より理解できるよう、そして後世に残していけるよう、日々心掛けたいものです。 |
 『相棒-自選エッセイ集』金子光晴・森三千代 出版社: 蝸牛社 出版年 : 昭和50年 「跋」(抜萃)より 『僕らは、お互いに先のことはあまり考えない方だったが、ただ、六十、七十と年令がすすむに従って、ヒフがたるんで皺が寄ることは、防ぎようがない。充実していた中身が少くなってゆくのだからそれは、当然なことで、あまり、じぷんでも、他人にも不快な感じを与えるような変化のしかたはしたくない。』 『相棒の彼女の方は、女の秀才型だが、僕からみると、なまじ文筆などを志したので、じぷんをつなぐ綱にしぱられた栗鼠みたいに、まちがえで僕の奸策にかかり、そのうえ、後半生を不治の病ひにかかって臥床というつらい目にあったまま、今日にいたっている始末だ。なにをしても、考えても、もうはじまらない。すでに人生はおおかたぬけがらになって、じぷんたちの遠くうしろにある。それだけに、たまにひまなときにふりかえってみて、たのしむということもできる。てなれたうんちゃんみたいものだ。人生は、痛苦という神経が多すぎるとおもって生きてきた。この神経をいっさい除去する方法ができたよとおもってみたこともあるが、もし、苦しみがなくなったら、同時に、楽しみもなくなるのではないかという心配ものこる。お釈迦という男は、なんでも都合のいいふうに考えてずいぶん人生を曲のないものにしすぎた張本人だが、彼の説によれば、苦楽は、一つものの表裏にすぎないことになる。その証拠には遠ざかってゆく苦は、楽と見境がつかないものとなるわけなのだ。』 『二人の二人三脚的随筆は、うまく走らうが、ころぼうが、知ったことではない。よむ人は、おかしければ笑うし、腹が立てば、腹を立てればいい、しかし、それほどのことはあるまい。元来、そんなに立派な文章をかく人間たちの随筆ではないから、タメになるようなこともない。その代りに、きらくだ。男と女なんか、こんなふうに生きても、五十年もながいあいだいっしょにくらせる、とわかってもらったらそれでいい。つまり、うら切ったって、浮気をしたって、元へ戻ったって、一向に気にもしなければ、波風も立たず、問題も、先方から避けていってしまうというわけ。また、貧乏なときもあれば.金の入ることもあり、そのふりあいはよくわからないが気にしない方がいいということなど、期せずしてうるところもあるとおもう。(昭和五十年初夏』 |
10/11頁―思い出の読書棚 『流浪の詩人 金子光晴』  『父・金子光晴伝 夜の果てへの旅』 (書肆山田)森乾 『父・金子光晴伝 夜の果てへの旅』 あとがき 森登子 『夫の亡くなった五月は、鳥の囀りがしきりになる季節です。梟など鳥好きの夫は、きっと鳥に身を忍びこませ、病でなしえたかった夢を捉えようとしているような気がします。 思い出してみますと、夫の「金鳳鳥」だけでなく、金子光晴の遺作も『梟は巣に』(昭和五〇年九月、角川書店)でした。鳥は古巣に帰るの諺どおり、みな鳥になって巣に帰ろうとするのかもしれません。森三千代の言葉にも、ひとを「乗せて不死の国へ導く」(『金色の伝説』序、平成三年八月、中公文庫)のは白鶴とあり、やはり鳥にまつわています。 私がわが家の鳥たちの行方を追うのは、自然の理のように思えてなりません。(二〇〇二年三月)』 父と母と、子供は 三つの点だ。 この三点を通る円周のうへで 三人の心はいつしよにあそぶ。 母よ。私たちは二度ともう 子供の一点を見失ふまいよ。 さもなければ、星は軌道からはづれ この世界は、ばら/\にくづれるからね。 三本の蝋燭の 一つの?も消やすまい。 お互のからだをもつて、 風をまもらう。風をまもらう 詩集『蛾』より 「三点―山中湖畔に戦争を逃れて」(部分) |
 大明敦さん  宮沢賢治「アザリア」の友たち  「猫大集合」  版画家・大野隆司さん 作家・北村薫さん 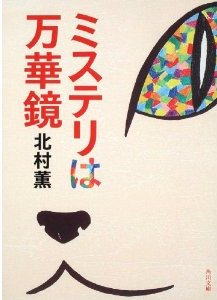  ミステリは万華鏡 ミステリびっくり箱 (角川文庫) (角川書店)  作家・重松清さん 角川文庫『卒業』より  |
12頁―『北武蔵散歩径―学芸員春秋記』 「さいたま文学館」の魅力 この冬、「さいたま文学館」が市民の足を集めた。当紙でも平成十八年に「秩父 山の文学」で縁ができて以来、「武者小路実篤と新しき村」、最近では「田山花袋の『田舎教師』から百年~田舎教師が愛した景色」展など、一つ一つの企画を楽しんだ。どれもわが町に縁が深いということもあるが、学芸員の大明敦さんの存在が大きかった。 大明さんはプライベートでも宮沢賢治の心友・保坂嘉内に傾倒する「アザリア記念会」の中心メンバーだ。『アザリア』とは花巻高等農林時代に彼らが発行した同人誌の名。嘉内の故郷・韮崎で活動に関わり、当館でも「「宮沢賢治とアザリアの友たち」を開催した。 わが町の「くまがや賢治の会」の勉強会講師に駆けつけてくれたこともあった。机上の学問でなく、文学ファンの心をくすぐる血の通った仕事ぶりだった。 その大明さんが異動となり、担当する最後の仕事となったのが、三月十四日まで開かれていた「文学館に猫大集合」だ。 この展示は収蔵品の中から〝猫にまつわるもの〟を拾ったもの。 埼玉ゆかりの文学としては加藤楸邨「猫」、鹿児島やすほ(寿蔵の妻)「はなとねこ」など。いずれも愛情溢れる世界が広がっていた。 メインは、もちろん版画家・大野隆司さんの作品。そして「ギャラリーGabo」と本人から寄贈された「猫版画」が並んだ。 大野さんが長く装画挿画を担当する作家・北村薫さんとの対談「猫と文学」も開かれた。 猫好きのお二人は自分の猫との暮らしを披露。また作家と画家が組んでどのように本を作り上げるのか、そのプロセスが示された。 今展は、作品を私蔵せず、たくさんの人、特に子ども達に見て貰いたいという画廊主の願いから始まった。 大野さんは谷中安規を知って版画を志し、また孤高の作家を現代に蘇らせた人だが、その人自身も版画を彫ることで、 「まず私が私を救った」 ……自己表現をすることで世界とつながっていくこと。そんな思いが重なり合った。 ポスターなどにも腕を振るった大野さん。自分も猫の好きな大明さん。会場には猫が登場する賢治の「セロ弾きゴーシュ」直筆原稿も飾られていた。 「ことばの力」 一月三十日 大林宣彦監督「その日の前に」の原作者重松清は、鬱屈した少年の心に寄り添う題材や、日々の生活を等身大で語る独白など、偽りない言葉が今日を切り取る。 その人が桶川へ来た。 作家は「ことばでメシを食っている人間」として話し始めた。今、ことばがもっている力が小さくなってしまったことへのもどかしさ・不自由さ。いつも、どうすればことばが復権するか、大人は子どもに何ができるか考えているという。 戦争で不自由した両親にとって、「平和」の象徴は「白いご飯」。子どもが腹いっぱい食べている姿をみていれば幸せだった。その揺るぎなさ、 迷いのなさ。 それに対し、今は物質的満足を求めてきりもなく欲求が高じていく。自殺者が交通事故よりも多くなった。どうしたら幸せをみつけられるか。 そのためには「想像力」を鍛えること。百%均一でなく一%の例外を尊重すること。大きな一つの幸せではなく、小さなたくさんの幸せをイメージすること。その時に文学が役に立つ。 いろんな人・いろんなことがあるとわかる。出会いの可能性に満ちている。今あなたが本を読んだことで、その本は命を得てリレーのバトンとなって数十年後の誰かに届くのだという。あなたがその未来の一人の命を救うのだと。漱石だってそうして読み継がれてきた。その可能性を信じ「本を読んで下さい」と、売れっ子作家はことばを結んだ。 秋には「アララギ展」が開かれる予定だ。 埼玉で「アララギ」といえば、鹿児島寿蔵。市内には生前を知る人も健在だ。田端で被災して後七年、熊谷で暮らした人間国宝の人形作家にして歌人にスポットが当たる。常設ブースには、熊谷で発行された歌誌『新泉』も並ぶが、まだ埋もれているものが多い。これを機に顕彰が進むことを期待する。 |
  新川菜園 平成22年3月28日 |
9頁下段―編集後記 ○春は些末な雑事に追われ、気候も「三寒四温」。慌ただしくも心揺らぐこの季節の変わり目に新聞づくりの大詰めを過ごした。 幾ら年を重ねてもこの頃の春の惑いは上手くやり過ごせない。その上に三十年来の花粉症。筆の進まない今号ではあったが、今回もまた嬉しい出会いがあった。 一つは石上寺の取材のきっかけとなったニュースソースのその大本の方と再会できたことである。知人から聞いた「本堂再建」の情報をお寄せいただいた方はもとより、そのご本人に改めて感謝申し上げる。そしてこの春、熊谷桜が健やかに育って、新築の香気溢れる大伽藍を前に花ほころんだ。 今日の桜花を見ながら、昔日の境内の華やかな桜模様が幻のように眼前に立ち戻った。近隣に暮らして御堂再建の晴れ姿を心待ちにしながら、自分の限られた余命を知っていた方の無念の声も、そのお連れ合いからお聞きした――時分の花と心得ることのできる覚悟。そして無心の樹木の確かな命の連なりを思う。桜は守ってくれる人がいてこそ花開く。人もまた同じ。当紙の周辺にいる方々のお陰で、わが町の歴史の今に立ち会えることが嬉しい。 ○いよいよ深谷の「まちの映画館」が新天地に移転する。新劇場のすぐ側には、まだそのまま他の歴史的建築物が佇んでいる不思議な空間だ。深谷のまちにこの後どういう風が吹くか。 そして、わが熊谷は? |
| さきたま新聞への たくさんの励まし こころより お礼を申し上げます。 次回は2010年6月 「21号取材の部屋」で、 お会いするのを 楽しみにしております。 |
 メール |
トップ |
