

Contents
�w�V�x���A�}�����琶�ҁx �����q������
�w���Ɠ��Ɏc��ĈΒe�𗁂т��Γ��āx�����d�Y����
�w�������w�̐N�������F�J��P�x���쒉�v����
�w���B�Ƃ��������������x���̂P�{���[�O����
�w���B�Ƃ��������������x���̂Q�ēc�@������
�w���a�̂��߂̖k���푈�W�x
�w���̓��A�L���Łx���J�F�q����

| �w�ς����������̌�̊�т͎v���o�ƂȂ�l���������x �V�x���A�}�����琶�� �����q������  �@������\�N�āA�����͖k���I�����s�b�N�J���Ƃ������A�����q������̂��b���f�����Ƃ��ł����B�����x���[�X�p�̏����Ȃ��̐l�́A���ă\�A�Ɩ��B�̍����x���ɓ�����A�V�x���A�Ŏl�N�̘ؗ������𑗂����B�ߍ��Ȑ풆���̓��X�������āA���̏t�A�Ď����j������������́A�S����F�̖�����l��l���m�ɌĂтȂ���A�l�̐��ɂ͉^���̕����ꓹ�Ƃ������̂����邱�Ƃ����x�����������B �@�������ɏ��W����āA��x�ڂ͑����A���ƂȂ��������ƁA�Ђ�k���̘I�Ə������������A���邢�͈ꏏ�ɉ��O�]�ɕ����A�P�����Ȃ���z���悪�ʁX�ƂȂ�A�őO���ɎU���������̗F�ƁA��������Ƃꂽ�����B���ɂؗ͘��ƂȂ��Ă���A�_���C(�A��)���Ȃ���A���y�ɉʂĂ��F�̐��͒m��Ȃ��B  ���c�ʐ^ ��������B��̕����p �@���a��\�l�N�㌎�A��������͋��ł̂��Ƃɐ����ċA�邱�Ƃ��ł����B���̐l�͌������B�u�������Ȃ����A���ė��Ȃ�������A�ꐶ�Ɛg�Œʂ����v�B���ꂩ��Z�\�N�A�Ȃ̏t����Ɗ��Y���ĕ�炷����̋��ԂɁA �I���S�[�����v����������ł����B�u���̎l�N�Ԃ�����ɂȂ�܂����v�ƁA��������B�u�M�a�̘J����]���܂��v�A���H�̓��t�̕\����ɕ��c�����̖����������B �@�V�x�����}���L �@���������A�����ɂȂ��Ă���̂͒��Ԃ����ƏW���Z�̂̉�B�u�V�x�����}���L�v�Ƒ肳�ꂽ�̂��܂Ƃ߂Ă���B �@���a�\��N�֓��R�ɏ��W���ꍑ���x���ɏA�� �[��ɈŖ�ɏ��铮���� �Ƃɋ����ďe���\���� �̋��̔ޏ����Âь���� �J���i�̉Ԃ��S�ӝD�F ����Ȃ新���炠���f�鐺 ���ɕ�����ᒆ�s�R ���Ă��Ȃ��_���C�i�A���j�̗�������Ɍ��� �K���ɐ������D�F�̐��� ���X�Ǝ��Ԃɖ�����e�� �A�邠�ĂȂ����y�ə �撣�����������_���C�Ɛ�������� �a�F�͂قق��݂��[�ƈ���� �҂��Łi�܁j�ɐ߂ē͂��悱�̈�O �B�҂ł��Ă�t������܂� �����̎��t�̊Â��������� �v���o�c��V�x�����̏t    �i���a�\�O�N�ɍ�������q�B�m�[�g�ɗF������������A�����͑}�G��S�������B  �@���������ɔM����簐i����l���������B�G���D���������������H�ɂȂ����B�j �@��̐��ɂ���� �@��������͑吳��N�A��{�����R���܂�B�q�포�w�Z���ƌ�A�\�l�œ���H�Ƃ��ĐΌ��ɕ���ɏo���B�ŏ��̒��������͓�\�̎��A��O���ƂȂ�u�����͌R���ɗp�͂Ȃ��v�Ǝv�����B���a�\�Z�N�̂��Ƃ��B �@���̌�A���a�Y�Ƃɂ͎d�����Ȃ��B���{�R�p���ނƂ����R����ЂŁA��s�@�����P���p�̖͌^����邽�߁A����F�s�{�̔�s��ɋΖ����A�����ŏ��W�ߏ��������B �@�����̂��ƂƂď����ȌR�����N�A�����ɂȂ邱�Ƃ��ł��Ċ����������B������Ⴂ�A���肩�犘�R�A�����Ė��B�ցB�\�A�����̌Փ��ɔz�����ꂽ�B �@���ɂ͎R���̒n���ɂ���A�H���ɓ����������n�̐l�����͊F�E���ɂ��ꂽ�Ƃ����B�����ŌP�����A�����ƂȂ����B���̌�A�H�����ł̖؍H�C�Ƃ𖽂����A���Ǝ����͍��|������B���Ⴂ�̕���Ő��т������A���O�]�̋�����(����͂���)�ɓ]���ƂȂ����B�Ō�̌�������邩��ƁA�w�n������Ă��Ĕs��B�u���������v�Ǝv�����B �@�����āA�V�x���A�ɑ���ꂽ�B �@�V�x���A�}�� �@�ŏ��ɉ��Ԃ����̂̓l�[�x���X�J���Ƃ����w�B�^�C�V�F�g����u���[�c�N�Ɏ���O�S�\�L�����[�g���̋�ԂɁA���������Ŏl���l�̓��{�l�ߗ����}������A���V�x���A�i�o���j�S���~�݂ɋ��o���ꂽ�B �@�l�[�x���X�J���̓^�C�V�F�g����Z�\���L���̒n�_�ɂ���A�X�Ɏ�����e�������ĂȂ��牜�n�Ɍ������B���n�тő�̂��A���o���A�H�Ղ�����Ă���́u�n���̖��؍�Ɓv�A��Ԃō������^��ė���Ƃ����Ζ�ԍ�Ƃ��s�����B��l����̃m���}�� �u����������̐H���ׂ��炸�v���S���B���m�Ȑ����͕s����������ŎO���S�l�����𗎂Ƃ����B 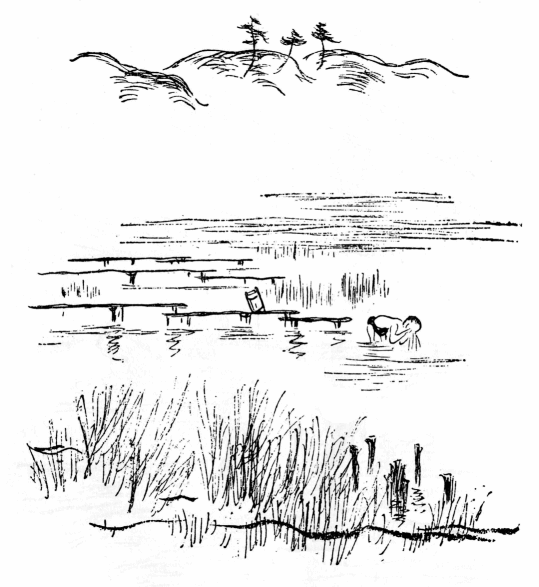 �G�E��x�k���u�ߗ��̌��L �Z �^�C�V�F�g�E�C���N�[�c�N�сv�\�A�ɂ�������{�l�ߗ��̐����̌����L�^����� 1989�N �@���̒n��́u���݂̃��V�A�v�̐S�����������B�S���̂��A�ň��܌ܔN�A�u���[�c�N�ɂ͐��E�ő�̐��͔��d�����ł��A�n��̋��_�s�s�ƂȂ����B �@���O�\�N�o���āA��������͓��\����̑�\�ψ��Ƃ��āA���̊X��K�ꂽ�B�̂̎���b���ƁA���n�Ɉē����ꂽ�B  �V�x���A�̑�n ���͐V���s�s�Ƃ��Ĕ���I�ɔ��W���Ă��� �@��ς������͎̂����̕��������ƁB�����̊��ɃS���̖̂悤�ɃL�Y��t���A��ᴂ��|���Ă����ƒ��ɊÂ����t�����܂�B�ł����p���Ə��ʂ̂������z�������̂����A���������������Ă���𐅑������ĐH�ׂ�B�������h�{�����͔������Ȃ��B �@�܂��A���߂̂����͌R������̂܂܂̊K���Љ�ŁA��̎҂��D������A�s���͂˂����s�B�ƌR�ɔj�� �s�������\�A���̂��H�Ɠ�����ŏ��̓~�ɁA�������m����������S���Ȃ����B�����Ɖ���A��������͓����@�������A���ꂪ�̗͉ɖ𗧂����B���n���V�A�̊Ō�w����̓Z�����C�h�l�`�̂悤�ɉ��炵�������B �@�}�����A�ԗ��X�Ȑl�Ԃ̎p�������B�Ɍ��ł͂ڂ�ڂ₵�Ă��Ă͐����Ă����Ȃ��B��Ɠr���ɐd������ĐH�ו��Ɗ�������ˊo�����������B��J�m�炸�̂��V��������m�l�͕��C�œD�_��������A�l���ς���Ă��܂����B �@�����A���V�A���O�͗D���������B�ŏ��͌����̕����u�T�����C���{�l�v���������ăs���s�����Ă������A���{�l�̋C�������킩���Ă���Ɨǂ����Ă��ꂽ�B����ē͎����̕��̉�����S�����ꂽ�B �@�}���̍Ō�̔N�͊y�������B�l�̉Ƃ̔_��ƂȂǂɏo�����A�̉a�̂��Ⴊ����H�ׂ���A���Ԃ���r�[���������Ƃ��������B �@��������͂����Ől������܂����B�\�A�̍��̎d�g�݂�m��A�u�����̂悤�ȕn�R�l�ɂ͂����Ă����B���̏Z�ސ��̒����v�Ɗ��������B��J����Ă���w�Z�Ɏu�肵�A�N�^�N�^�̑̂ɕڑł��Ďj�I�B���_��ُؖ@ ���w�B���{�ɋA������݂�Ȃŋ��Y�}�ɓ��}����Ɛ����������B �@�̍��̏��͒m�炳��Ă����B�A���͗D�G�ȍ�Ƒ����珇�Ԃő���Ԃ��ꂽ�B���̉\�Łu�A��邼�v�ƒm��x�x���āA�i�z�g�J�őD������̂�҂����߂ɍ~�藧�����B �@�����ɂ͐Ԋ����U���āA���}�̏o�}�������B���ɒ�������F�ŏW�c���}�����͂��������̂��A�����W�Q���邽�߂ɁA���ꂼ��Ƒ����Ă�Ă��ăo���o���ɂȂ����B��������͌�Ō����ɏo�����Ď葱���B�����œ��}�����͎̂����Ƒ�{�Ŏs��c���ɂȂ����l�ƁA���̓�l�����������ƌ���m�����B �@���A��������͍��͂����Ȃ��Ό��\���������̐��ˉ��h���C�u�C�����ł₫����t���C�����������B�C�w���s�Ȃǂ̑�^�o�X�����X�ɉ��t�����ꂽ����ł���B �@����ɁA�\�A��m�낤�Ɓu���\����F�J�x���v�������B�ψ����Ƃ��Ċ����B�K�K�[���������u����ɌF�J����o��������A�u�������z������v�ňꐢ���r�������D���c�Îq�������ċΘJ��قōu������J�����B 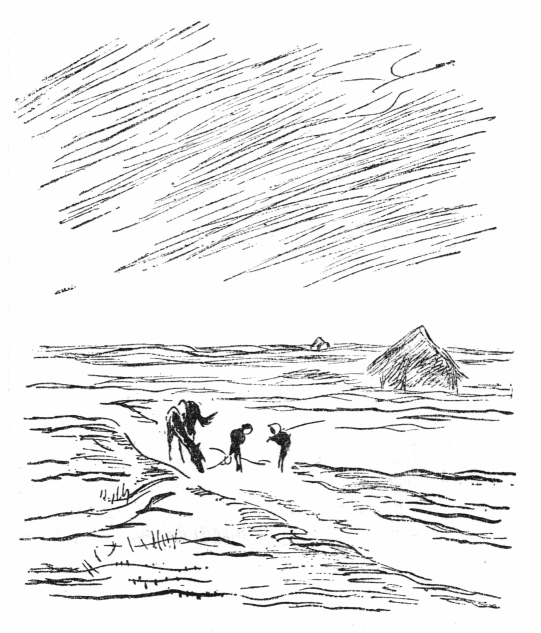 �����琅�ˉ�����p�����c�Îq����c�q�đ���������L�i���� �E�[�������q������ �@�����Č����B�u�푈�͎��̏��l���~�]�������߂ɋN�������́A���̖���� �����Ɍ������v�B�푈�̔��[�́A�I�a���ɂ��Ă��g���L���p�����ɂ��Ă��ł����グ����n�܂����B�W�c�E�l�͉��Ƃ��Ă������~�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �@���̃}�l�[�Q�[���̎���͂�����s���l�܂�A�K���V�������オ����Ɗm�M���Ă���B �@���Ԃɂ͎�Ƃ��Ă��鏑�E���G�������Ă������B���̒n�Ń��V�A���w���o���A�F�J�����A���́u���Ђ��v�ō��������Ă����B�Â��z����̈�Ƃ̎ʐ^�A���o���������Ă����������B�����̎d���ƍD���Ȃ��ƂƁA��r�ɂ�萋������������̖T��ŏt������Y�����B�u��J�Ȃ�Ă��Ƃ͂Ȃ������ł��B�݂�Ȃ��ꂪ����O�ł�������v�B  �u���c�Îq�ƌ���v��k�V�� ���a54�N12��16�����s ���c�Îq�ƌ���@���\����F�J�x���Ŏ�� �@���\����F�J�x���i�����q���x�����j��Ấu���c�Îq������ނ����A�\�A�̕����Ɛ��������ǂ��v�͏\�ꌎ�\���ߌ���F�J�s���ΘJ��َO�K�z�[���Ŗ��Z�Z���Q���A�\�O�\���N�̉��c����̋M�d�Șb�����k�`���ōs���L�Ӌ`�������B(��) �@���c�Îq����͐�O�����̍������z���ă\�A�ɖS���B�����̐�������납�������A���X�N�������ǂœ����A�����A���o�ƂƂ��āA���̔������\�A�Ŋ���A����當�������̒��œ��\�F�D�̑傫�Ȗ������ʂ��Ă����B �@�܂����{�����Ƃ��āu���̈ꐶ�v��痂܂��������Ă������ۓI���D�Ƃ��čL���m���Ă���B(��) �@���\����͓c�q�đ����i��ʌ����y������F�J�x�����j�̈ē��Œ��ҁA���b�R�Ȃǒ����̔������R�����Ȃ��߂Ȃ���A�u�܂����t�ɂ͓��{�ɎQ��܂��v�Ə\�ꌎ���\�A�ɋA�������B  |
| �w���Ɠ��Ɏc��ĈΒe�𗁂т��Γ��āx �@�����d�Y����  �uNo.17(��28.8)���d�X���Љ�����{���R���ځ`�}�g�̊T���������哹��]�ށB(��������Ĕ@���Ɍ�ʗʂ����Ȃ����ɂ��ǂ낭)�v�@�\�����̌����������̒��Ɠ��\ �u�F�J�D�Е�������v���V �� �@���̍��q�́A����n��̍ĕ҂ɐs�͂������E���̐��V�����瑡��ꂽ�B���a60�N�ɂ��̎ʐ^��ڂɂ����A��������̋����ɂ͐ϔN�̎v������ꂽ�B  ���Ɠ��ɂ� �@�R�z���݂��Ɏf�����܂�A�����킹���l��ځE�����d�Y����ƌ��t�����킵���B�b���F�J��P�ɋy�ԂƁA���������ƂɁu�����ɂ͐�̒܍����c��Γ��Ă�����܂��v�B�G�܂ŕ`���Đ������ĉ�����B���Ղ̖{�Ɩ{���A�F�J�����Ă̘V�܂Ɛ푈杂Ƃ͈ӊO�Ȏ�荇�킹�����A���a��\�N�����\�l���A�ČR�̔����퓬�@�a�@�ɂ��W���C�̍��Ղ��A���̖ڂŊm���߂邱�Ƃ��ł����B����͏ĈΒe���܂Ƃ��Ɏ��Γ��ĂŁA�[���Ɗ}�Ƀo���o���ƏŒ��F�̔��_�����܂�Ă����B �@������Ղ��I����čĖK����ƁA����l�͂܂��\���N�O�ɋL�������e��ǂݏグ���B�u���ꂪ���ׂĂł��v�ƁB �@���͂̌��т͂������B �w�u���������M�������낤�v�c�c�ƁB���͂����Ƃ��̐Γ��ĂɎ����ƁA�����������Ȃ��Γ��Ă����낢��Ǝ���̗���Ɨ��j�̕ϊv������Ă����悤�ȋC������B����͎������Ɋ������́u�v���v�ł�����B�������́u�푈�v���́u�F�J�̐�Ёv�ɐl����Ȃ�̎v���o��������́A��x���̐Γ��ĂɎ�������Ɩڂ���v�������A�Γ��Ă������Ɖ������Ă���邩������܂���B�x  ���ԏ�i���Ɠ����j�̋��̐Γ��� �s�����ʂ肩�猩�邱�Ƃ��ł��� �@���ݒ��ԏ�̋��ɂ���O�E�܃��[�g���ɂ��y�ԑ喼���ẮA��S�O�\�N�O�̑n�Ɠ������炱�̓X�̃V���{�����������A�����̐��܂����Ɠy���̕ǂ������͂ɍR�����ꂸ�A�j��|�ꂽ�B���Ă͏ォ��[���A�}�A�Α܁A����(��)�A��(��)�A��d(�y��)�ƘZ�ɕ�����Ă���B��N�Ԃ͏Ă��쌴�ƂȂ����~�n�̕Ћ��Ƀo���o���̎p�Œu����Ă����B �@���̌�A���̉Ƃ̉��̂ō���V�c���h�Ƃ����F�J��̏h�E���䗷�ق����̌��ւ��̍ہA���̓��Ă�����B�����J�[�ʼn^�сA�������ĂĂ݂�ƒ���̖�O���̈ꂪ�����Ă��āA�Ƃ͑S���g�����̂ɂȂ�Ȃ��B��ނȂ������Ύ��̊�����Č`�������B�����̐ጩ��q����̒��߂͑f���炵�������B���A���ڂ蕽�����N�A���ٔp�ƂƂȂ��\�N�Ԃ�ɓ��Ă����Ɠ��ɖ߂����B �@��������͍Đݒu�ɂ�����A�ʂ肪����̐l���l���ǂ̕�������ł�������悤�ɒ���ƊƂ͐V�������肩�����B�����ɐ��ՌA��\�z�����߂Ă���B �@�\�ŕ��e��S��������������́A�Â��E�l�Ƌ��ɊŔ��₳���A���݈ꖇ�ł��Ă���������e�����S����������S�ŐՂ��p�����Ƃ����ӂ����B �@��P�̎��͎l�B���̓��̂��Ƃ͂悭�o���Ă���B�Q�Ă�����}�ɖ��邭�Ȃ�A�����Ԃ��Ȃ��h�Ђ���A�����Ŏ����o���ƌ��߂Ă����u�L���_�[�u�b�N�X�v�Ƃ����G�{�O���̕�݂����Ɋ������B �@��s�@������s���A�R��̓y������̍H�ꂪ�^���Ԃɕ��ꗎ�����B�H�n���ď�V�̕��֓������B�����A��ʂ̏Ă��쌴�ɏĂ��c��������Ɠ|�ꂽ�Γ��Ă����������Ƃ́A���ł������قɏĂ��t���Ă���B �@���N�O�ɑ�a���������A�u���O�B�̐����͂��Ă���B�����ɂ͂܂����������������Ƃ�����v�Ɣ����̎R�̐����̌ÖɎ�ĂĊ���|�����Ƃ����B�V�܂̐Վ��Ƃ��Ė{���̂ǐ^�Ō����̏��a����������������A�u�l���̓h���}�A�N��������͎������v�ƌJ��Ԃ����B �@�Ă̓�����A�X���������B�䎞�J�̉��A���Ă������ƕς�炸�Â��ɗ����Ă����B |

| �w�������w�̐N�������F�J��P�x �@���쒉�v����  �@���a�l�N�A�F�J���T��̍����@�i�����E�������ȁj�ɐ��܂��B���a26�N�䐳���w�i���]�쒆�j�ɕ��C�B�����ԕ��T�[�N����g�������Ɍ��g���A���ɂ͎s�c��c���ƂȂ�B���݂��F�X�ȉ�̗����߁A���Ԃ���u�Ђ���v�̂悤�ƕ���Ă���B �����̒m���Ă���O�l�̘b �@���삳��͒��w�Ő��w�Ɨ��Ȃ��������B�����̘b���Ԃ���n�}�������Ȃ��痝�H���R�A�����Ȃ��̂��������B�u�����̒m���Ă���O�l�̘b�����܂��v�Ƃ��̑̌������n�߂�ƁA�F�J��P�̊G�}���܂��܂����S�����B �@�悸���߂́A�F�J���w�ŗB��l���𗎂Ƃ����e�F�ē��N�B���̍��A���Ƃ͂Ȃ��Ċɑa�J�����R���H��i�[�J�̏����s�@�E������s�@�̉������j�ΘJ��d�ɍs���̂����ۂ������B�⏕���̔��̎d�����B�ɉ��U����ƁA��������݂�ȂŁu�ۂ��@�v�Ő����т��A�������ŋA��邻��ȓ��X�B���������̓K�L�叫�݂����Ȃ��̂��������A��Ҏu�]�̔ނ͕w�ɗ�ޗD�G�Ȋw���������B �@�Ό��ɏZ��ł����ނ͈�x�͖h�ɓ��������̂́A�F�B����肽�{�����ɖ߂����B�Y�ꕨ���C�ɂȂ�A�z�c�����ē�K���ցB���̘L���ňꔭ�̒����e���y���B���삳��͈�Ԃ̗F���������B �@���͏��w�Z�̓���������������N���B������������ߏ��̎q�ǂ��B�̊i�D�̗V�яꂾ��������B�����ɔ�э���Ŗ��𗎂Ƃ����B������m��l�͐��삩��͓��C�������Ă����Ƃ����B �@�̂͐���̐앝�����������ɉƂ����č���ł��āA��ʂ肩��͐�ʂ��݂��Ȃ��قǖ��W���Ă����B������A�l�������Ė��l�ƂȂ����Ƃ͏Ă���ɔC���A���ꂪ�݂Ȑ�ɕ��ꗎ�����B�߂��̔ѓc���@�Ȃ̎q�ǂ��������悤�ɐ�֓��������A���e���u����ȂƂ���͑ʖځv�ƈ�������グ�Ė��E�������B �@�Ōオ�A�߂��̔������̂��ł��B�Ԃ�����Ԃ��Ă��āA�����e���ĂƂ��ɖS���Ȃ����B �@���삳�g�͂��̓��A�p���c��ŐQ�Ă����B���~�������w���̌Z�������݂�ȋA�Ȃ��Ă��āA����̂��������ƘZ�l���Ƃɂ����B��P�O�Ƀ]���]���Ɖו�������ē����Ă����l�B�����āA�Ȃ�ōs���̂��ȂƎv�����B��ł킩�����̂����A���O�Ɂu�`�P�v�Ƃ����ĕČR�̃r������s�@����܂���Ă��ċ�P�͗\������Ă����B �@��K�̉J�˂͊J���Ă����B��s�@�̉��Ŕ�ыN������A�w�̕��ɏƖ��e�������A�^���̂悤�ɖ��邢�B���ꂩ��ĈΒe���~���Ă����B���؋����̊C�A�����w�Z���R���Ă����B����_�Ђ̗��̕��։�邱�Ƃɂ����B���]�Ԃ������ē����A�����܂ő������B�Ƃ͌F�J���̎��Ɏ���Ė����������B �@�Ђ́A�N�����Ȃ�����ޏĂ����������B�Ă��쌴�ɓy�����c���Ă����B�����A�c������Ɓu�h�[���v�Ɖ������ĕ����オ��B�V�������̂͏�v�������B�����A�������S�ɗ�ߐ�Ȃ������Ɍ˂��J����Ƌ�C�ɐG��A��u�ŔR���オ�����B�c���Ă��Ă������͍���������A���܂��Ă�����݂̂͂ȑʖڂɂȂ����B �@�\�ܓ��ɋʉ����������邱�Ƃ͒m���Ă��āA�s�c�̗F�B�̉Ƃɍs���ĕ������B  �@�Ď����L�^�����n�}�Ō��Ă������邪�A�Y��ɒʂ�ɉ����ďĂ��Ă��āA���Ō����Ɠ���傤�ǏĂ��c���Ă���B�ČR�͂�قǐ��m�ɔ��������̂��B�����āA�F�J���_��ꂽ�̂͒�����s�@������������Ƃ����������邪�A���̉������H����S���Ă��Ă��Ȃ����A����͈Ⴄ���낤�B���삳��͒��߂��������B�u�������̔N�i���\��j�ɂȂ�܂����A�푈�͂����Ȃ��ƌ��������܂��傤�v�B  �@���̌�A���O�̒�����̌��҂����l�������グ���B �@���̓��ɐ��܂ꂽ�Ƃ����������Ȃ𗧂����B �@�Y�a����A��̉��ŋv���Ԃ�ɌF�J�ɗ��Ă���Ƃ������̐l�́A�u��͎��O�ɋ�P��m�蒁���ŏo�Y���܂����B�����������玄�͐��܂�Ă��Ȃ�������������܂���B���̐��������Ă悩�����B�����Ƃ����ƒm�肽���v�ƌ�����B �w��25�a�̂��߂̍�ʖk���푈�W�x��� |

| �w���B�Ƃ��������������x���̂P �@�{���[�O����  �@�{������Ə��߂ĉ�����̂͐��N�O�̐푈�W�B�ΉP�ŕ��������āA�����Ƃ�����̌��R�[�i�[�̒S���������B�d���ΉP���ɂ͗͂������āA�����Ă����������B�V�x���A����A����͋��R�̂����H��œ����A�_�Ƃ̎d������`������V���z�B�������Ƃ����B ���B�J��c���N�`�E�R�ł̑̌� �@�{������͏��a�\��N�O���A�u�肵�Ė��B�֓n�����B���ɏ\�l�A���R�̐q�포�w�Z�Ő搶�Ɋ��߂��āA�n�_�̘䂪�������֍s���Ώ\�����̔����Ⴆ��ƕ����Ċ�їE�B �@��e�͂��O�ɂł���킯���Ȃ��ƐS�z���A�ꏏ�Ɏu�肵����������l�����ǂ͎���߂��B �@�푈�����łɖ����ł���A��ʁE�Q�n�E���̎O�������������g�D���ꂽ�B���ꂪ�Ō�̐��N�`�E�R�ƂȂ����B �@���B�̓\�A�����߂邽�߂̓��{�̍Ŗk�̐������������B���A�������̊֓��R������ɑ����Ď�̉��B�Ō�̎�i�Ƃ��ď��N�`�E�R���W�߂�ꂽ�B �@���{�̌R�͂͒��߂��Ă����Ȃ��B�A���D�Œ��N�C����n�����Ƃ��̋����������ƁI�@�C������ČR�����͂̐��]�����`���Ă����B�������ˁB�u�D�̒��֓���v�ƍ��߂��|�������B�O���Ԃ��������Ȃ��Ƃ����~����𒅂����B�u���ԓ��ɏ����ɗ��邩��v�Ƃ������Ƃ��������A�K������������Ċ��R�֒H�蒅�����Ƃ��ł����B �@���C�����͍̂��͏ȑ����i�\���S�E�j�A�R���͍����Ƃ��낾�����B�ꌾ�Ō����Ε����́u���邢�v�A�u�����炵���v�A�u�Œ��ꒃ�v�B�N���̕�[�������������B���̎w�����Ŕ_�k�ƌR�������ɖ�����ꂽ�B�R�̂Ƌ`�E�R�̉̂��̂킳��A����ȉ̂��̂��Ɠ{��ꂽ�B���B�ł͍L��ȑ�n���Ĕ��_�Ƃŏ��J��ɊJ�����_�n�Ƃ���B�Ă������͈�N�͋x�k�c�Ƃ��ċx�܂���̂����A��������グ�Ă����B  �@�����炩�����ꂪ�킩��悤�ɂȂ�ƁA�����֍~��ėV�тɍs�����B �@�y���݂������̂́A�n�����H�ו��ł͂��邪�A�g�E�����R�V�Ƒ哤�̕�����������o�̂悤�Ȃ��������\���i�}���g�E�j�����y�����ĖႤ���ƁB�����u�߂��L���x�c�������Ă����B �@���n�̐l�̂Ƃ�������������邱�Ƃ��������B��������ƎႢ�l�݂͂ȘA�s���ꂽ�B�����͂킴�Ɖ������𒅂Ċ�ɓD��h���Đg�� ����B�u���C�t�@�[�Y�v�A���߂����Ē�R�����i���Ȃ������l�̏퓅�傾�����B �@���ꂪ��]�A�����ɓ���\�A�R���N�U���ė���Ƃ������ƂŁA�퓬�ɉ���邱�ƂɂȂ����B�Ō�̈�T�Ԃ̐킢���B�G�̐�Ԕ���Ɉ͂܂�A�C�������B��ɂ͔�s�@�A�����̖��|��钆�𖽂��炪�瓦�����B�g�[�`�J�Ƃ����āA�y�����@��Z�����g�Ŕ����Ɍł߂����̂ɏe����J���Č}�������ˑ䂪���������A���̖̂��ɂ͗����Ȃ������B�@���̌�͖������ԂŁA�G�̃L���^�s���̉���_���Đi�ݏo�Ĕ����𓊂����ނƂ������B���Ɠ����ɂ͎����̔Ԃ��������A�s�킪���܂�A�h�����Ė��͏��������B���������ƂȂ������A������͋����̏��e��A�������̓}���h�����Ƃ����ŐV�e�ŁA���Ă�킯���Ȃ������B�ؓ��̏�ɓS����ׂĐ�Ԃ��n���ė����B �@�H�ɂȂ��ă\�A�̃~�n�C���ߗ����e���ɑ���ꂽ�B�O�N�ԍޖ؍H��̎d���ɂ����B���{�ɋA���Ă��瓭���Â߂ɓ������B �@�{������͋`�E�R�̑O�ɂ͊C�R�Ȃ̐������ɂ��u��A�����ɓ�l�������i���Ă������A�ҋ@���Ă���܂��W���Ȃ��A�`�E�R�Ɏu�肵���Ƃ����B���a�\��N�Ƃ��������s��͌����Ă����̂ł͂Ȃ����Ƃ����͍̂������猾���錾�t���낤�B �@���Z�\�O�N�Ƃ������A�b���Ă���ƁA���̐l�B�̑̂̏��ʂ�߂��A���ݍ��܂ꂽ�u�푈�v���A������̂��Ƃ̂悤�Ɏv��ꂽ�B  �@���������v�ے��ꂳ��͎�����푈�̌������B �@�Y�a���̂悤�ɍ��Z����Ⴂ�l�̎p���݂��Ȃ��B �w��25�a�̂��߂̍�ʖk���푈�W�x��� |

| �w���B�Ƃ��������������x���̂Q �@�ēc�@������  �@�ēc����͏��a�X�N�A���B�̎�s�V���ɐ��܂��B���y���D���ŁA�����J���i��㐷�������������B�������ԒB���������ςݗ��ĉ��y�����悵���j���o�āA��ʘJ���𗧂��グ���B���̌�F�J�ւ͈�Ð����E���Ƃ��Ă���ė����B ���̕��͂a����Ƃł��� �@�ēc����͏��w�l�N���̎��܂ŁA���e�̊��m��Ȃ������B���͕s�݂����ŁA��q�ƒ듯�R�B�u���̐l�͓�̑����l�ł����v�ƌ����B���e�͐̂̂��Ƃ͈�،��ɏo���Ȃ������B �@�����g���̎��ɍ쐬���ꂽ�g����ۏ��鏑�ވꖇ�����ƂɎ��s�����Ē��ׁA�B�������_�́A�u���͓얞�B�S���������̃G�[�W�F���g�������v�B �@�ēc����̉Ƃ̓N���X�`�����������B����Ȃ̂ɁA�u���̐l������Ȃ��Ƃ������̂��v�Ǝv�����B�������������l�\�Z�l�̒����l�����͑S�����𗎂Ƃ����B �@���I�푈�ɏ��������{�����V�A����D��������̂��A�ɓ������i�֓��B�j�Ɠ얞�B�S���A�����씼���������B���̌�A�S�������Ƃ������ڂŊ֓��R�͋�������i�����J�n�A�u���{�ŋ��̌R���v��搂�ꂽ�B �@�얞�B�S�������̖����a�Œ����R�̔��C�������ł����グ�Ă���͌R�����Ƒ��B�ꋓ�ɖ��B��苒���A�u�����y�y�v�u�ܑ����a�v���X���[�K���ɖ��B�鍑�����������B �@�\�N�ԂŎO�S���l��ڕW�Ƃ�����{����̈ږ��v�悪���Ă�ꂽ�i���ۂ͕S����j�B���B��B��Ђɂ���Č��n�̔_���������Ă����_�n��P�p�B�u�������֍s���Ώ\�����̔������Ă�v�ƊÌ���M���A���֊J��c�▞�B���N�`�E�R����W���ꂽ�B �@���S�̒������Ƃ����͍̂��̃A�����J�̂b�E�h�E�`�Ɠ������B�����Ƃ́A���{���A����肪�o��قǂق����������B�̖��s���Ȏ�����ړ��Ăɂ������́B�R�ƌ������������Â�A�x����Ă���ė��ċ�J������ʐl�Ƃ͂�������āA�ґ�̌����s�������B  �@���e�́A�}�]�i�������̌Ós�y�g�i�j�Ƃ����Ƃ���ɐ��Y��Ђ�������B��ԍ]�Ƃ����Đ앝���O�A�l�L���������͂̐�����������������グ�ēƐ�B���{�ƌ�̑�m���Ƃ��o�������֓��R�̂��߂̉�ЂŁA������x�[�R���A�����A���X�A�L���r�A�A�L�q�Ȃǂ����R�̗Ⓚ�ɂ։^�B���̏��L�n�͔n�ʼn���Ďl���|����قǍL�傾�����B �@��Ђ̓y�g�i�Ƃ����~�`�̑傫�ȏ�A�����l�̂˂��₪�O�l�����B�ēc����̖��̗V�ё���͎O�҂݂Ŕw�������������ő�p�l�̃L�N�����B�Ƃ̃s�A�m�ƈꏏ�ɒe���Ă����B �@���w�Z�͓��{�l�ƌ��n�̐l�͕�����Ă����B������B���́E����������A�����l�ɂ͓��{����������B�@���B���q�́A���B���́u�킽�������v�����������B���{�̏��̂ł͕��y�ɂ�����Ȃ��̂ō��ꂽ�悤���B �@�ꊦ���k���@�������ƂāA �@�@��������悤�Ȏq�ǂ�����Ȃ���B �@�@�܂��������́@�킽�������B �@��ɐႳ�ց@�~�����ƂāA �@�@���܂���悤�Ȏq�ǂ�����Ȃ���B �@�@�܂��������́@�킽�������B �@���e�͎���҂������B�k�C������㋞�����Ȑ��w�Z�ɓ��w��A���������̌����ɖv�����A�V��̃^�i�S�������B�������ʼn͐쒲���ɎQ�������قǍ˒����Ă����B�����A�k�x�̍ϓ�a�@�ɏ]�R��́A��s�V���Ɍ���i�̌R�オ�J�Ƃ����R�莕�Ȃœ������B���Ԃ̏]�R�Ō�w��������Ƃ͍ϓ�a�@�Œm�荇���A�������l�͂��̎��Ȉ�@�ɋ߂��B �@�푈���I����ƂƂ��Ēǂ��邪�A���������̐l���g����ƂȂ��ĎE����A�{�l�͒������Y�R�ߗ��ƂȂ�B��Ɣ퍐�\��l�̂����B��l���Y��Ƃꂽ�͈̂�҂���������B���Y�R�R��Ƃ��ĉ���^���ɉ�������B�A���͏��a��\�ܔN�B��͂��̓�N�O�ɐ��㎀���Ă���A���̕�O�Łu�������O���������Ă��܂����v�ƍ��������B �@����A��Ǝq�������g���ė��鎞�̂��ƁB���߂͓��{�l�S�l�Ŕn�ԓ�\���A�˂Ă������A�s��Ɠ����ɒ����l����O�֕���o���ꂽ�B�K���H�ו��Ɛ��͎��グ���Ȃ��������A�w�̍����R�[����������~�����������A���̋�J�B�D��������ʼn����������B��͂����ς����o�Ȃ��Ȃ�A�܃����̒�͂��̂������������₦���B�w�����Ă������A�u��������ł���v�ƌ����Ă���͎�����Ȃ��B����Ɛ������R�[�������̌s�ŏ\���˂�����đ������B�Z�Έȉ��̎q�͎E�����A���ʂ��B����ȏŎc���ǎ��̔ߌ������܂ꂽ���A�������n�����̂ɓ��{�̎q��a�����Ă������l�͑ŎZ�����������̂��A�Ǝēc����͌�����B �@���̓����s�̍ہA��p�l�̃L�N����������Ƃ͊�痊��ł��n�Ԃɏ悹�邱�Ƃ��ł��Ȃ������B��ł킩�������S���s�E����Ă����B�푈�ň�ԋꂵ�߂���̂́A���A�q�ǂ��B���������R�������������킯�͂Ȃ��Ƃ����̂��A�ēc����̌��_���B�֓��R�͂������Ɠ������B�u������ɂ��ꂽ�����͐����l�����ɓh�Y�̋ꂵ�݂𖡂키�B �@��\�l�܂Ő��������́A���B�ʼn������Ă����̂���̂܂܁A�{�l�͋ꂵ�݂��Ȃ��S���Ȃ����B�Ȃ����������l�������ȒP�Ɏ��˂�̂��B�����̕��̎��Ȃ���ēc����͓{������ɁA����Ԃ�A�܂��M�ق�U�邢�A�푈�̔ߌ���`�������Ă���B �w��25�a�̂��߂̍�ʖk���푈�W�x��� |

| �w���a�̂��߂̖k���푈�W�x �@��P��́w���a�̂��߂̖k���푈�W�x���J���ꂽ�̂�25�N�O�̂��Ƃ��B �@�������A�Y�a�ł̓W���������l�����������オ��A�����a�@�i�������a�@�j�����ǒ���v�ے��ꂳ��炪�F�J�ł��J�����Ɛs�́B �@������s�ψ����ɋ��q�������������B   �@�i2007�N�j�����\�Z���A���������́u���a�̏��v���苿������A�I�[�v�j���O���������̂́A�E�Z�ԍݏZ�ʼn���o�g�̎o���w��e�B�[�i������ȑ��z�̈Ӂj�x�̎O�����t�������B�{���݂��i���Z��N�j�E�݂�����i���w��N�j�͂�������Ɍm�Â����Ė���ČܔN�i�����j�B���ɂ݂�肳��͎��܂ʼn���ň炿�A�c���A�\�c���͉����̌��҂ł���A�܂����𗎂Ƃ��Ă���B �@��l�́A�u���a�̗��́v�A�u�T�g�E�L�r���v�͋���ł����B���t���i���X�P�b�`���Ă����̂́A�������P�����т���Ƃ̊֓c���g�������B��������B���b���Ă���T��ŗ܂���ł����݂�肳��B���������Ɏ������������Ȃ����킹�ďW�����A���̕s�v�c�ɗ͂��B �@�F�J��P�̔閧 �@�F�J�͎O�S��\�]�l�̊w���a�J��������̊w�Z�Ŏ���Ă���B�Ƃ������Ƃ͈��S�ȏꏊ�������Ƃ������Ƃ��B�����C���R�ɕς���Ă���A�ČR�̔�퓬���F�E�����n�܂����B�������P�ł͓�������悸�Ă��Ă��甚�����n�܂����B  �@�R�ݏG���s�ψ����́u�F�J��P�͏I��O��̂ƌ����邪�A����͊ԈႢ�v�ƕt�������B�|�c�_���錾�͊��ɏ\�l���Ɏ������Ă�������A�u�I���v�ł���B�@������Ƃ����Ĕ�Q�҈ӎ����������Ă͂����Ȃ����A���{�̉��Q�ӔC�Ƃ������͂��邪�A�F�J�s������ҁA�S�̋��ɂ����Ăق����ƌ��B �@�@ (�F�J�s�Ή��Z���^�[�ɂ�) |

| �w���̓��A�L���Łx ���w�Z�P�N���Ŕ픚�������J�F�q���� �@�x�b�g�^�E���̏����ȃM�������[�̊ŔɊāA���s�ψ��S�s�����̏��œ��O�g�́u�Ăт����v�������Ă����B  ���܂ł��������͂Ȃ� ���Ȃ��̂ق�Ƃ��̗͂��ӂ邢�N���̂͂������͂Ȃ� ���̓��A�Ԗ����܂��M���ɂ�ʂ��ꂽ�S�̏��肩�� ���������܂ʗ܂����Ȃ������Ȃ� ���܂����̗��ڂ��� �ǂ��ǂ��Ɛ푈�����^���������点�� �Ђ낵�܂̑̏L�����Ȃ������Ȃ� �Ăт����i���߁j���O�g �@�����������R���d�Ȃ�A�L���̌�����̌��������̂��b�������o�����B�Ƃ���͐�t�������s���c��w�̃X�e�[�V�����M�������[�B���a�s�s�錾�����Ă��锪���s�̕��a���ƂƂ��čP��́u��\���ʐ^�W�v�ɂ́A�����~�߂�Ⴂ�l�����������Ƃ����B  �@���J����͏��w�Z��N���������B�Ƃ͌�K�����ԁB���̍��ł��̎r���|��Ă���쉈���̌�ԂŗL���Ȏʐ^�̕���ł���B�K���A�̎肪����z���Ȃ���������Ƃ͖����������B�����肳��ׂ͈����ׂ��Ȃ��A�����q�ǂ��̉Ώ��ɐH�p����h���Ă���B��ɂ͒��̖��������Ől�Ԃ��܂�d�Ȃ��ė���ė����B �@���̓���������a�J�Ƃ������ŁA�ߌォ��Z�킽���ʼnj���ɍs���\�肾�����B���J�����������݂����ĉƂɋ삯�߂����B���ꂪ���������B�����ł͒��ڕ��˔\�͗��тȂ��B�l�̒�͘H��ŏ㔼�g���œ|��Ă����B�ꂪ�T���ĒT���āA�����ė����B�^��������Ő@������炪������Ƃނ����B�u��s�@�͋��낵���ˁv�ƈꌾ�B�����������܂����炻�̂܂��ʂƌ���ꂽ���A��͂ǂ������ʂ̂�����Ɖ�����^���A��炩�����������B�u���͂��������ˁv���Ŋ� �̌��t���B�o�̓V�~�[�Y�p�A��ƌ�����r�֍����P���C�h���c��A�����ƒ����������Ȃ������B���ł������h�[���̒��ɂ͓���Ȃ��B�Z�͔����𗁂сA���������̃K���X���˂��h�������܂܂������B �@�ꂪ�����Ō����@���āA�܂��������ɒ��y�̒��ɖ��߂��̂������ƌ��Ă����B���̕�͏����Ŋŕa��Ǝ��ɑ���������ɁA�T���ɂȂ�ƁA�w���a�J�ɍs���A�e�B��S�������ǎ��̎{�݂��b�����ɏo�������B���J���u���̑�������āv�ƌ����Ɓu���ꂳ��͖�ɂȂ�A���Ă���ł���B�䂪���������Ⴂ���Ȃ���v�B �@�����͔n�Ԃ����Ă����B�R�s���ŕ�炵�A�n�̈����ɓ��Ă�����́A�Ă��Ղ֏����ċ��������n�������ė���ƁA�Ȃ��߂Đ������Ŏ�����B���Ɖ��ɔ�ł����A�ޖ�͂�̏�ɐQ�鐶�����������A���v���Ƃ���ȔN���ŕ���������͐����Ǝv���B���̐l�ɂ͂ƂĂ��ł��Ȃ��B�u�S�̖L���Ȑl�ԂɂȂ�v�Ƃ����̂��ƌP�������B �@�Z�N��A��͎l�\�O�œˑR�|�ꂽ�B�����a���B�������đ��ʂ̕��˔\�𗁂тĂ����̂��B���������@�����Ƃ܂�Ȃ��B���J���Z�N���̎��A�q�ǂ����� �̐����ɂȂ����B���w������ŋA���Ĕ��e�@�֍s���A�|���Ȃǂ̎�`���������B�����������̂͗[�т�H�ׂ����Ă���������Ƃ��B �@���̌�A�莞�����Z�𑲋Ƃ������J����́A�ۈ�m���u�]���ď㋞�����B�Ƃɂ���Ǝo�ɊÂ��Ă��܂�����ƓƗ������ӁB�����āA��N�܂ŗc�t�����߂������Ƃ������A���͎l�N�O�܂Ō����̘b�͕��A�O�Ō�������͂Ȃ������B  �@�����ƌm�Â��Ă������b�p�̑��L���ŊJ����鎖�ɂȂ����B�搶���u���Ȃ��A�����̂��Ƃ�b���Ȃ����v�ƌ����������B���ł́A�����s�̕��a���ƂɎQ�����A�������o���Ă��邱�Ƃ����w�Z�Ō��悤�ɂ��Ȃ����B �@�q�ǂ��B�Ɂu��l���Ԉ���Đ푈���N���������ɂȂ�����Ƃ߂Ăˁv�ƌ����ƁA�j�̎q���u�l���撣���Ă�߂�����v�ƕԂ����B���鏗�̎q�́u���A�Ŏd�����ɍs���v�B���������ɘb���ĉ��������B �@�L���ł����̔N�㌎����w�Z���n�܂����B�̉A�Ɋ���u�������ŁA�S���̎��������ŃJ�b�g���ċ��ȏ��ɂ����B���������������B���������Ȃ��Ƃ���ꂽ�X�ɗ��萁�����B���R�A�����Đl�Ԃ̖��̗͂͂������Ǝv�����B �@�����s�͍L���Ǝo���s�s�ł���B�����s����قɂ͏Ă��c�����L���s���ɂ̕ǂ����ߍ��܂ꂽ�ԗ�肪����B�����Z���̈ԗ�ՂɌ��������Q�Ă�����������B���A���w���ɂȂ��Ă��������x��Ō�������Q�������B���̕�ł����l�̖��������ɍۂ��āA�^����ɍ��ƂɎ����̕ꂪ�픚�҂ł���ƍ������ƕ��������ɂ́A�ƂĂ��V���b�N�������B�����������b��B�������������S�����߂��B �@�����炱���A�����͗a���������t��`���Ă����Ԃ��Ă����̂��ƐS�ɐ����Ă���B�P������̐��C�Ɉ�ꂽ���J����́u�C���Đ����Ă���v�ƌ��ɂ����B��C�ɂȂ����畉���Ă��܂�����ƁB�u�ǂ�Ȏ����l�̂��߂̗]�͂��c���Ă����Ȃ����v�ƌ����Ă�����B���̕ꂪ���������������Ă��ꂽ�B 2008�N8��8����t�������s�ɂ� |

| �@ �@����ꎞ�������Ȃ����B�ӂ�ɂ��������̐��B�Ă̍����Ԃ��Ȃ��Z���ƂȂ�B�u���l�܁@�Ă̋L���v�����̋G�߂̓��W�ƒ�߂Ă���A�O��ڂ̉Ă��߂��䂭�B �@���N�͔͈͂��L���āA�F�J�ȊO�ɍL���▞�B�̘b��ɂ��y�B����{�ȂǂŌ��������Ă������Ƃł��A�ڂ̑O�ɂ�����̌���������ƁA���̌l�I�ȑ̌��Ɉ��|�����B���̓����ƁA���t�̗��Ɉ���v���ƁB���̐l���ǂ̂悤�ɂ�����z�����̓��X�����тĂ������Ɏv�����炷�B��������������c�c�@����Ȏv����������܂܁A���쓔�ė����ɏo�������B�����̓V�C���������A������̂��V�l�ɂ�鋟�{�̊Ԃ͉J�������Ȃ��ł��Ă��ꂽ�B����A���R��v�́u�����h�̍~�a�v���e�[�}�Ƃ�������̍s��G���ς�@��������B���̊�ւ̌�������̋F��̏�i�ɏd�Ȃ����B �@�ԉ̉��v�ׂĂ��āA�F�J�ԉΑ��ɒ����̈Ӗ������邱�Ƃ�m�����B�ԉ��܂ŁA�����ăA�i�E���X���������鋗���ŁA���߂Č����B���ƌ��Ɉ������荞�܂ꂽ�B��P�̋L�����S�邩��ԉ͋��ƌ��������͂����C���낤���B �@���~�����A�H�����i�ސΏ㎛�֎ʐ^���B��Ɏf���ƁA�N���[���Ԃ��V�������ě������Ă���B�����֏Z�E���܂����a�����ق���߂�ꂽ�B�㌎��\�����܂ł̊��W�ŌF�J��P�̃R�[�i�[�ɏĂ�������o�W���Ă���Ƃ����B�S�Ă����{���Ɩؑ��̂���t�l�����̂��Ƃ��v���o�����B�R�������邨������^�яo���ۂɍ��j�ɕ�������Ώ��̒ɂ܂�����B �@�Ă��I����Ă��A�������͏I���Ȃ��B�X�ɐV���Ȑ킢���J��Ԃ���A�Ύ�͐₦�邱�Ƃ��Ȃ��B���́A�Ɩ₤�����p�͂Ȃ��̂��낤���B |

�������ܐV�� |
�g�b�v |
