

「お前の近年の仕事は平野の仕事が主になつて居るやうだ。お前はそんなに平野が好きなのか」と聞かれる。「私は平野が好きとも嫌いとも、はつきりとは言はれません。それは唯私勝手なので、唯そんな風に運命が廻り合せて来て居るに過ぎないのです」と答へるより外に仕方がない。 全く僕は平野についての好悪の情を、はつきり表明出来る様な感激も衝動も持つては居ない。唯僕は平野の中から生れて来て、平野の上で死んで行く様な運命になつて居るのだらう。僕の心は平野を信ずるのだ。僕の情は平野を親愛するのだ。仮令ば他家の子でも好きな可愛い子供がいくらもある。それでも万一其子等が自分の子供と喧嘩をすれば、自分の子供に加担するお袋の心と同じ様なものだらう。 僕は山国の人に向つて、平野を誇つたこともない。又山国と平野とを比較などしたこともない。僕も山国に友達もある。親しい知人も居る。僕が行けばそれ等の山人が僕の野人を引張つて歩いて山を見せてくれる。本当に山は美しくて、偉大で、よいナーと思つてしまふ。それでありながら一向に手帖の白い頁がふさがらない。カンバスが白いまんまで幾日もよごれ出さない。僕には矢つ張り野の様に、一も二も無い愛情と信用が、未だに山へ向かないのだ。借家をするのに、何ケ月間は決して追ひ立てを喰はさないといふ証文を欲したい様な憶病がつきまとふ。何とも仕方が無い。之れは神様が僕に与へたものだとあきらめるより仕方が無い。 僕は平野に生れた運命を、よいとも悪いとも感ぜすにうけるだけだ。僕の躰にくつついて居る土の臭も、なまづの様にのらくらした気の永い性情も、みんな仕様が無い。平野に生ずる自然の現象の様々も、平野の景色の、のんべんだらりとした低能さも、僕には面白いのでも可笑しいのでもない。唯あるがままを、あるがままに受け入れて、唯信じて、其中で嬉んだり淋しがつたりして居るに過ぎない。 僕は子供の時分から今も、つくづく平野のつまらなさ加減に愛想をつかすこともある。腹の立つこともある。あまりに面白くも可笑しくも無さ過ぎる毎日の平凡さに、あくびをしいしい年を重ねた。 榛の木枝の葉が北風にふるひ落されて、路ばたのたんぽぽの花が咲き出すまで、関東平野の村々は、唯灰色に眠つた。ゴーツといふ秩父颪の冷こい御見舞は毎日続いた。それでも冬は「風が吹かねーぢやあ天気あ続かねー。いい塩梅(あんべ)いだ」と嬉ばれる。だが毎日二里に近い町の小学校への往復に、躰中隙間なく北風に馳け通られるのは、なんぼ子供の僕も寒かった。ふところ手した握り拳手(こぶし)の指は、いくら呼吸を吹きかけても容易に言ふことを聞く様には動かなかつた。家へ帰つて貰ふ饅頭は、数日仏壇に供へられて居たのだから、皮が乾破れて白い粉を吹いて居るのだつた。それでも饅頭はさういふのが当り前だと思つた。 僕は此春太田の呑龍様へ子供を連れてお詣りに行かねばならぬ。私も小さい時に母に伴れられて、呑龍様へお詣りしたことがあつた。山といふものを傍で見たのは之れが始めであつた。私の生れた村の近辺では、呑龍様の在る処は金山太田(かなやまおおた)と言ひ慣されて、呑龍様よりは、其金山が珍らしいのだ。 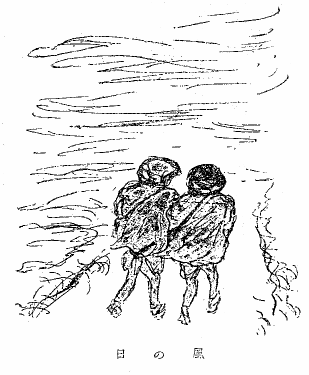 《挿絵・風の日》 土色に濁つた利根川を始めて渡船で越えた。大きな大きな河の中程へ渡し船が出た時分、川上の方から何だか腫れ切つた様な黒い大きなものが一つ浮いて来て、段々こつちへ流れて来た。船頭が「ヤア土左衛門だあ」と言つた。さうして何か投げたけれど当らなかつた。船頭はハハハ……と笑つた。船が向岸へ着いた時、船頭は又川の方を見て居た。「あれ未だあすこに居らア。あいつ何処から来やがつたんべか。大分呑んでやがらナア」と言つて又哄笑つた。僕は母にあれは何だと訊ねても母は教へなかつた。僕はどうもあれが人の様に思はれてならなかつたが、人にしてはあんまり大きい。大きい川にはあんな恐ろしいものが居るのかしらん。といつまでも心にかかつた。 大人になつて、画描きになつてから、東京に住んで居る僕は父の村へ年頭に行く。正月の村道には未だ春の色は浮ばない。路傍の小川のせきに菜つぱの屑や大根の尻つぽが引つかかて家鴨の黄色い嘴がそれを突つついて居る。村の中へ這入れば少しは人の話し声もする。時々鶏が鳴くのが聞える。それでも停車場を出て村と村との切れた田圃道には、人に遇ふことは極めて稀だ。桑畑の瘠せた幹が風に微かな音を立てて居るばかりだ。霜どけの道をうねりうねり行く。路傍の草の中には未だ餅草の影もない。村家に遠い風の野面の早春は、なかなか緑の恵みをうけぬ。僕は路傍の石に腰を下して、「何だかつまらないなア」と溜め呼吸を吐く。 平野の中の丘は、のんべんだらりの野の景色に、いくらか気を利かせた神様のしやれであらう。武蔵野に梅の咲く頃、僕は浅川の宿に尻を据えて、塵ツぼい路ばたに画架を立てた。 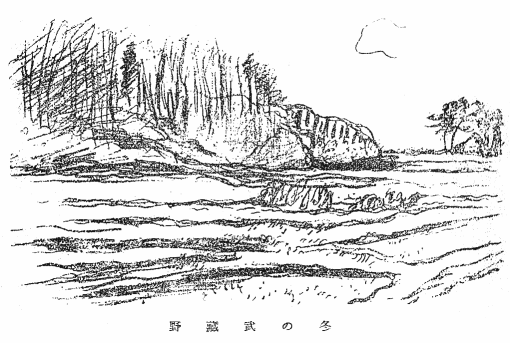 《挿絵・冬の武蔵野》 「どうだね、此処等は風はひどいかね」と暇さうな後に立つた親爺に聞いた。「はアちつたア吹くね。だが今年アどういふもんだか、あんまり吹かねーからいい塩梅だ」「でも雨も降らねーね」「雨どこぢアねー。乾き過ぎて仕様がねー」と言ふ。成る程乾いた路だつた。日南(ひなた)に背中を温めながら、小三時ばかりカンバスをなでて居る間に、画面はざらざら砂土が塗り込まれて、筆が動かなくなつてしまつた。「お前さん何処だね、東京かい」と親爺が聞く。「私かね、私は武州だ」さつさと絵の具箱を片づけて宿へ帰つた。 「お湯は今晩もお気の毒さんで御坐います。早く御飯を差上げな」といふのを聞いて、二階へ上つて二時間許りすると、女中が飯を運ぶのが例だった。そして皿は小鮎の真つ黒に煮たのがついて居たから、「梅の咲く時分鮎とは珍らしいね」と言ひながらランプのそばへ持ち上げたら、蝿が四五匹鮎の背中にくつついて居たから喰ふのを止めた。  《挿絵・沼ばた》 武蔵野も山寄りの丘地は、風が吹かないでも雨にならない。幸に丘の変化の恵みがあるが、人の気は余りに長くてぢぢむさい。 好くも思はぬ、悪くも思はぬ。唯時々の嬉しさ淋しさに即く関東一面の野は、今の僕の画生活にとつては大きい故郷になつてしまつた。僕の生れた村人も、共処からあまり遠からぬ利根川の流れの、三十里四十里と下つた両岸の村人も、唯平野の中の故郷の人になつた。 僕は印幡沼の端の、ぽかぽか暖い春先きの径を、道草を喰ひながら歩く。下総の野には春の訪れることも早かつた。日南の堤の腹には笊を持つた老爺が摘み草に余念なかつた。沼端の村には梅が咲いて、二月の田家はおつとりと静まり返つた。ぬるむに早い沼水には、枯れ葭の残つた茎が夢の様に立つばかりだ。むぐつちよの水面を立つ羽音が、僕の来た後の方に聞えたが、鳥は影を見せない。 僕は沼端の土の塊りを拾つては、やたらと沼の中へ投げ込んだ。それから土の中の葭の芽をさがした。彼れは固い根を沼土の軟かい中へ横へ横へと張りひろがつた。さうしてちよびりちよびりと青い芽ぐみを持つて居る。やがて彼れが柳も草も茂りかくして沼水の上に生ひ跨る夏の準備は出来て居るのだ。 春先の野には人が少くて、僕は何だか淋しくなつた。ぽかぽか暖い野の静かさは、唯太平の淋しさだ。 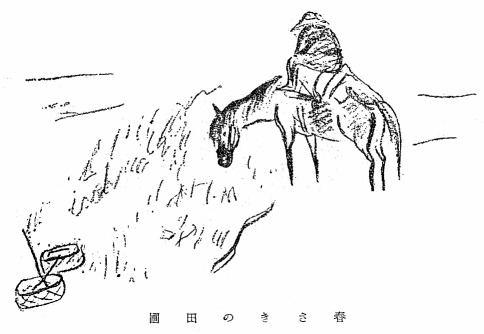 《挿絵・春さきの田圃》 僕はよく川堤の上を歩く。風が少し暖かくなつて、土堤の枯草の黄土の色がほんのりとした緑の色に変つた頃は、漸く野に生れた甲斐がある様な心に、僕は甦へる。 土堤の向ふの田圃には、ぼつりぼつりと春田の仕度が始まつて田の土を掘り返す男の笠にあたる日影も暖かさうだ。尻をからげた僕の脚の下駄につく土も何だか軽くなつてよい気持だ。土堤下の草家の前には白い煎餅が幾つも幾つも蚕かごの上へ並べて干してある。僕は土堤の草の上へ腰を下して、先づ煙草を吸ふのだ。扨てあの煎餅は幾枚あるかなと数へて見るのだ。十枚二十枚と数を読んで居る内に、すつかり何枚あつたかは忘れてしまふ。又数へ直す。又忘れてしまふ。仕舞いにやうやうつまらないことをして居ることに気がついて止めてしまふ。其処で腰を上げて、又ぶらりぶらりと土堤を行くのだ。 手拭をかぶって、股引をはいて、背中に毛糸の帽子(シャッポ)をかぶせた子供を背負つて、手に徳利を提げたかみさんに遇ふ。「おかみさんあすこの村に宿屋がありますかね」「宿屋かね、あるにアーありますだ」「何軒もあるかね」「なアに一軒しか無いですよ。ひよつとすると休んでるかも知んねーが、大方泊まれましようです」「なぜね」「大師宿でがすからね」 大師宿、どうせ僕も大師詣りの様なものだ。お賽銭の代りに鉛筆と紙を持つた自然の参詣人に過ぎないのだ。 堤の上から見渡す野面の春草は、萌え出す緑の色に染つて、灰色の死から漸う漸う平野は甦へつたのだ。 堤は徒らに長くして、向ふに見える森のある村にはなかなかたどりつけぬ。其なかなかたどりつけないのが寧ろ嬉しいほど、野に春が来たのは嬉しい。 (大正十年三月・中央美術) |
 平野雑筆目次トップ |
 メール |
 トップ |
