

contents
| 『10号』 2007 11/5 まちを彩るひとびと その7 『愛は全てを完全に結ぶ帯である』 写真家 北 熊市さん 『11号』 2008 1/21 まちを彩るひとびと その8 『いくつもの時代こどもを見つめて』 吉田美智子さん |

まちを彩るひとびと その7 愛は全てを完全に結ぶ帯である  北 熊市さん (赤城町) 北熊市さんは故郷のまちと人々を 鋭いカメラアイでとらえる。 昭和8年柿沼に生まれ、 熊谷市制施行を記念し熊市と名付けられた。 曲がったことの嫌いな性格は父譲り。 小作農の父は、戦後、農地解放時のどさくさ騒ぎに 「本家の土地を貰うわけにはいかない」 と乗ずることがなかった。 その混乱期、働きながら夜間高校に学ぶ。 熱心な美術教師の下、好んで絵を描いた。 仕事場の郵便局には 近くに住む大野百樹画伯が時々見えた。 一級先輩が写真店を開いたのをきっかけに カメラを購入。 写真ブームに沸く昭和25年のことだ。 15年後「熊谷白陽写真会」入会。 アマチュアに徹した写真人生である。 |
| カメラを手にして 若き日々、特定郵便局での理不尽な激務には心身をすり減らした。仕事は生業と割り切って、生きていくために写真に向かった。昭和33年、「うちわ祭写真コンテスト」特選。これがカメラ道の幕開けとなる。 埼玉国体の年、昭和41年に歴史ある建物をテーマとしたコンクールがあった。そこで県知事賞を受賞したのが、写真の師・八木橋信吉さん、その作品は「市立図書館分室」であり、北さんは「大里村―根岸家長屋門」で県議会議長賞を受けた。 阿部道山がその表彰式で述べた。 「この世はすべて日々刻々と変わる。その一瞬を写真は切り取る」 この言葉によって道が定まった。 わが町の歴史的風物、縁の人々に向き合いシャッターを切り続けた。 この年はまた、敬虔なキリスト教徒である北さんが洗礼を受けた年だ。芸の道は厳しい。幾多の受賞後、好きな写真が苦しみの道となってしまった。《求めよさらば与えられん》の言葉を信じ、心に満たされるものを求めて、教会に通うようになっていた。 神に捧げた命、一から出直そうと「結果を求めない生活」に辿りついた時、夢にまで見た大きな賞を手にした。時に昭和56年であった。 以後、市立図書館写真クラブや「白陽会」で後身を指導、熊谷を記録する写真展・出版物の企画編纂等には必ず北さんの名がある。 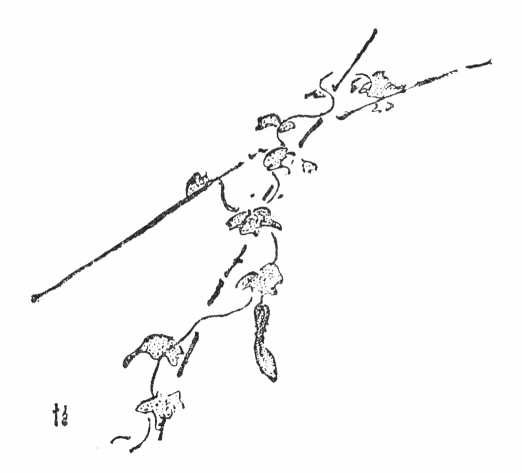 田植風景(柿沼) 昭和46年 写真は時代の証言だ 北さんは、わが町の顔「駅北口の熊谷直実像は武将姿ではなく、蓮生法師としての姿であるべきだ」と言う。平成11年にまとめた写真集「人間讃歌 北熊市の唄」巻頭には、先日亡くなった書家野口白汀による聖句「愛は全てを完全に結ぶ帯である」がある。  頁を繰ると、田植・建前・葬儀・入学式等の光景が懐かしい。壊された校舎、駅舎、旧家。甲子園、お祭り。そして、名士から無名の庶民まで、存在感のある人物や家族の肖像が並ぶ。  塚本家 写真集カバーを飾った写真は、昭和56年撮影。  23年後の平成16年、再び同じ場所、顔触れで撮ることが出来た。その組写真「二十三年の歳月」は読売写真大賞に輝いた。この年のテーマが「家族」だったから、「手応えがある」と応募。「一人一人の表情が豊かで、レンズをのぞく自分の気持ちまで幸せにさせられた」と言う。 そして、花へ この10月4日、「熊谷白陽写真会写真展」に出展した写真は、ひまわりを中央に配した「陽炎」など、カラーフィルムの花々五点であった。 花を撮るようになって数年、なぜ「花」かと問えば、「花は人の心を和ましてくれるから」……花の美しさに惹かれる歳になっていた。 花や自然界にはアンバランスな色の組合わせがない。全体として調和がとれ、飽きがこない。だから写真でも、作為せずそのまま再現する。当然、カラーとなった。   「可憐」 自分が感動した、その熱さを伝える、それが腕の見せどころだ。更に付言する。人物写真は、如何にその人らしさを引き出し、肉薄するかが勝負だが、花も同じこと。信頼関係があり、理解し合って、その美しさが表現できる。 北さんは取材時、出展する五点を箱から出して並べて下さった。 「どういう風に並べるか」 「人の目線は左から右へ流れる」 「ものの位置はどこでもいいのではない。流れにストーリーがある」 ……含蓄のある言葉だ。置いては返し、位置が決まる。更に展覧会場で、全体の配置を構成していく。  展覧会場 展覧会場まちの記憶 最近通い詰めたのが、無惨に取り壊された熊谷市本町の一画だった。パン屋「アルザン」から「高木肉屋」まで、戦災も免れた歴史的な佇まいがご時勢で消えるとあって、モノクロ・ネガ・リバーサル、あらゆる状態で記録に遺した。 床屋では、図らずも閉店を知らずにやって来た常連さんの散髪光景が撮れた。「アルザン」では、家族一同が集合して記念撮影という日に熱を出した方がいて、おかみさんが残念がった。町工場からは役目を終えた精密機械が東南アジアに旅立って行った。カメラを嫌って納まってくれなかった人もいるが、そんなことや表面には見えないものも含め、数々の物語が読み取れる写真となった。   本町一郭 メッセージ 本棚には様々な写真集、郷土出版物、そして時代を切り取る写真雑誌「DAYS JAPAN」ファイル等が並んでいた。文机には、熊谷市文化連合が着手した「熊谷文芸」創刊号に向け執筆中の原稿用紙が置かれていた。題して「人間再生の鍵」。今日の風潮には人一倍の憂慮を抱く。 愛するということは、命を捧げるということなのに、人間としての責任が疎かになり、未来に遺すべき資源を食い潰している現代人。勝手すぎて我慢のきかない人間ばかりのおかしな世の中だ。これだけは言っておきたいと、思いの丈を綴った。 この8月、所沢雑学大学で戦争について講演した。「孫達への証言」第十八集へ応募した兄の体験による海軍従軍日記 「トラック諸島からの帰還兵」がきっかけだった。 きっちり項目別にまとめた講演原稿には戦後の動き、文明論等のデーターが並んでいた。過去を知り、地球が上げている悲鳴を聞き取り、大切なものを忘れないでいようという論旨だった。 風貌、語り口はあくまで柔和、それでいて内に外に厳しく向き合ってきた視線の確かさ。その作品の重さを受け止められる人間でありたいものだ。 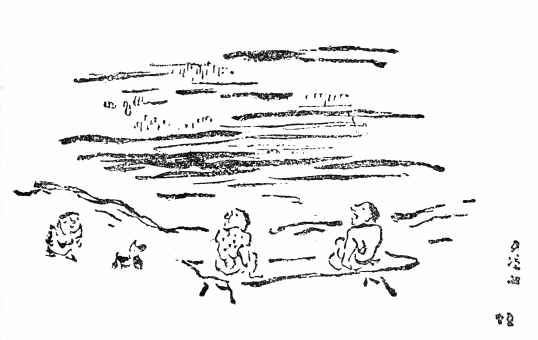 写真集「人間讃歌 北熊市の唄」より |

| まちを彩るひとびと その8 いくつもの時代こどもを見つめて  児童文学作家 吉田美智子さん (ペンネーム中野みち子) 吉田さんは 「幻の村」新川の太田家と同じ祖先を持つ 久下の旧家に生まれた。 昭和21年、県立熊谷高女卒。 絶対的な教員不足の混乱期、 進学を断念し久下小学校に就職した。 5年後東小学校に在籍しながら、 埼玉大学教員養成科修了。 以後、川口市で教壇に立ちながら、 「中野みち子」を筆名に児童文学の執筆を続ける。 退職後、母の看病のため 熊谷に戻ったのが平成元年のこと。 更に故郷の民話を再話、語りの実践に当たる。 |
戦後間もなく 校長退職後助役まで務め、新生熊谷の教育行政に献身した父、思いやり深い母の下、吉田さんは五人兄弟の長女で「美智子はいるのかね、いないのかね」と言われるほどおっとりと、空想好きな子だった。 女学校では皆の憧れの的巣山先生が国語担当、熱心に学び、中でも文法が得意だった。長女が大切にされた時代、何不自由なかった少女時代を、戦争が一変させた。 家は空襲で全焼。哲学好きの父の世界思想全集、戯曲集等の書物も燃え、一陣の風にふっと散っていった。 衣服は全部焼け、ララ物資(進駐軍放出物資)のブラウス、ゴムぞうり履き、髪を結うこともできない17歳のみっちゃん先生は、土手や元荒川で観察ばかりしていた。覚束ないオルガンを弾き、新刊書を買っては読み聞かせた。 男先生は軍服姿、カリキュラムも教科書もない時代。昭和22年、荒川堤防が決壊したキャスリン台風の際、泥に浸かりながら新川の生徒の家を訪問したこともあった。 敗戦後、極度の混乱の中にあったが、世は文化国家復興に未来の望みを託していた。 市街地に転任した後、川口へ就職し、音楽専科となった。高学年の男の子にいい鴨にされ職員室に帰るやショボン。「心臓でやり通した」というのは、朝礼時のオルガン伴奏のことだ。  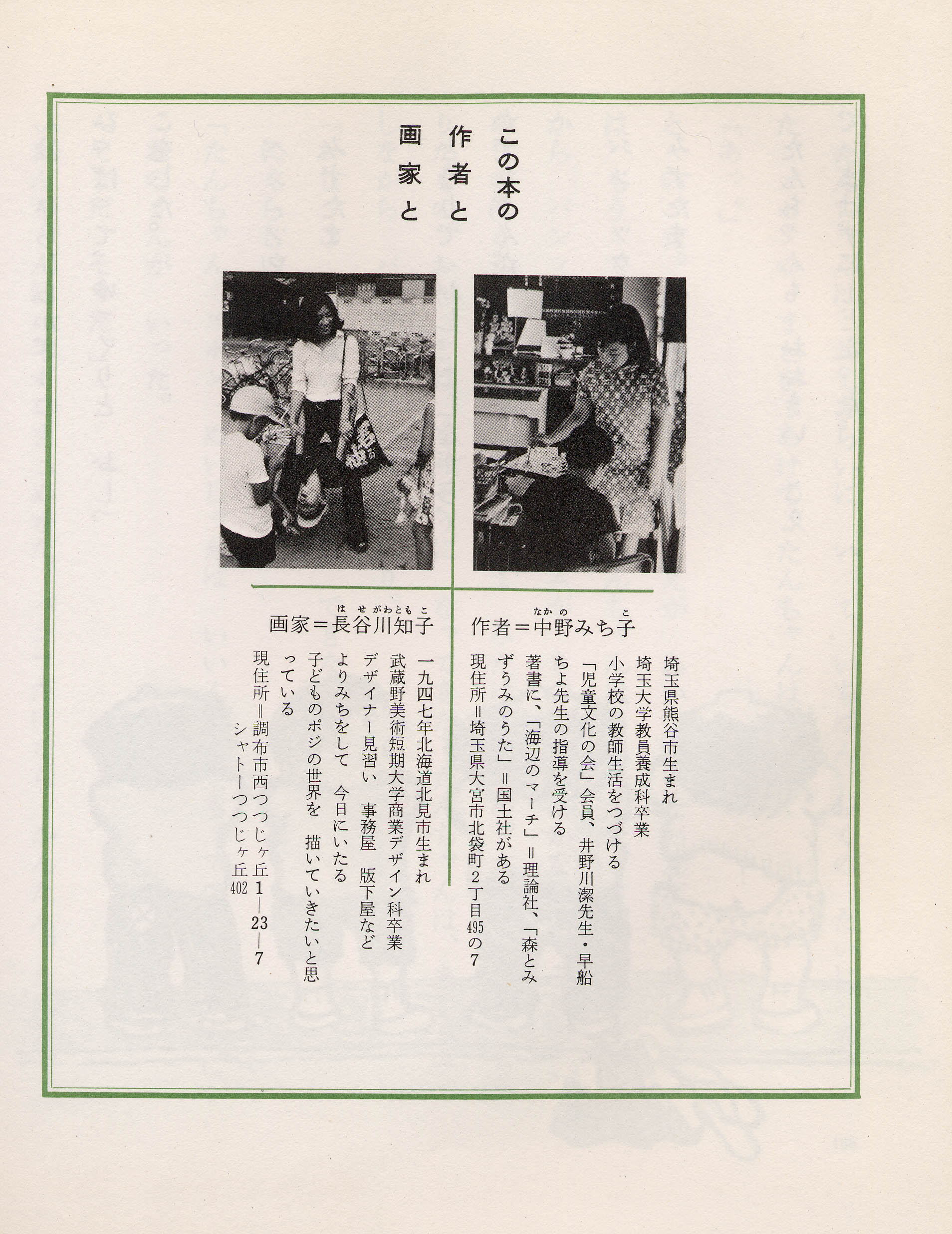 それを乗り越え担任となり、作家となった頃、「先生のおとおりだい!(初版本)」挿絵を担当した画家長谷川知子さんが、一日教室に張り付き、取材している。記事冒頭の写真は、その挿絵と共に、当時真剣に児童書作りに取り組んだ人達の熱意を伝えている。 |
師との出逢い 両親の次に吉田さんを育ててくれたのが、井野川潔先生。文学を志し上京して来た早船ちよさん(「キューポラのある街」で一世を風靡)を育て、後に結婚した雑誌編集者・教育運動史家である。 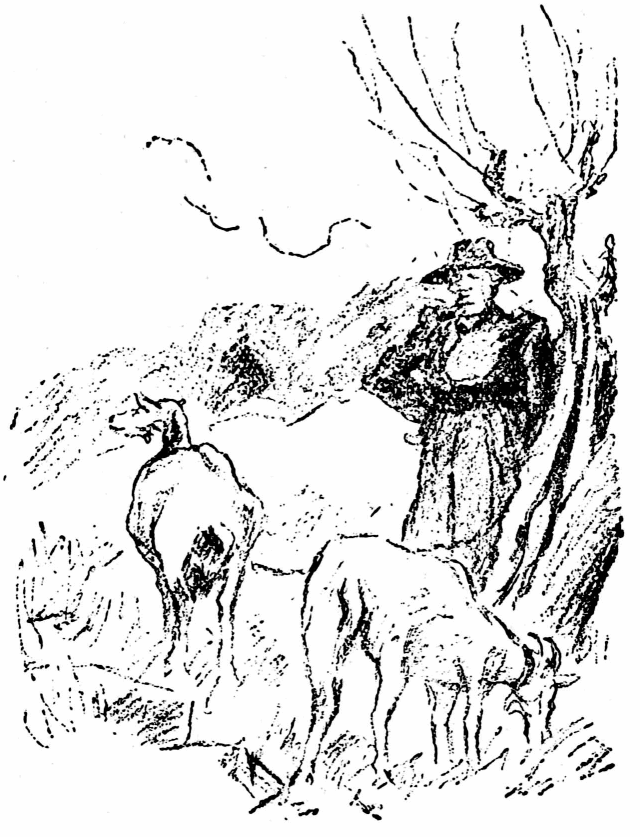 井野川・早船夫妻は浦和で「児童文化の会」を開き、後進を指導。月例会は埼玉大学の寮や銀行会議室等で、先生や主婦20人程が作品を持ち寄っていた。 昭和38年頃、友達に誘われ入会したのが30代だった吉田さん。それまで一人で書くことに向き合い、日本教職員共済組合「文芸広場」に投稿、掲載作も多かった。だが、自作のどこが悪いのかが知りたい。「仲間がほしい」の希望が叶い、川口の鋳物工場見学会に初参加した。 師には駄目出しされたことは一度もなく、何処かしら誉めてくれた。「先生も大変だったでしょうね」と振り返るが、その薦めで児童書の名名門・理論社から「海辺のマーチ」を出したのが、昭和46年。 |

吉田さんは義弟の暮らす北海道の森と山を舞台に取材を重ね、営林署に赴任した父とまき達家族、対立する労資の人間模様を描いた。社会矛盾に目を見開かされ、人を恋うることで成長していく中学生のまきのなんと魅力的であることか。 その後「森とみずうみのうた」が北海道から生まれている。「先生のおとおりだい!」は30刷を超え、10数万冊を刊行。昭和60年刊「シャクシャイン物語」は、江戸時代に松前藩と和人(シャモ)に対して蜂起したアイヌの悲話で、著書中最長編となった。 『ふと、前の方の雪の中に、カンリリカは黒いかげを見つけて、立ち止まった。熊(キムカムイ)?そんなはずはない。それでもすばやく、山杖(キムンクワ)に山刀(タシロ)をくくりつけて、槍(オップ)を作る。親熊が地にふせた。子熊が走りよった。 カンリリカは、槍(オップ)をさしあげ、雪の中に眸(め)をこらした。熊が立ちあがった。カンリリカは、槍(オップ)をささげたまま、近よる。熊(キムカムイ)ではなかった。人間だった。長い刀をさした和人(シャモ)の男と女と女の子ども。』 大酋長の息子とキリシタンとして落ちのびた足軽の娘との出会い。鮮烈な戦いの物語は少女の視点で書かれた。二人は結ばれるべくして、ついに結ばれない。清い恋と最期の絶唱。だが師は、それゆえに、 ―アイヌ民族の偉大な叙事詩の「ユーカラ」に一つ、つけ加えるか、それにも増してうつくしくも、すがすがしい― と評した。 |
学校で 教師に成り立ての頃、ノートによく詩や短歌を写していた。思い出すのは藤村・牧水等。俳句を嗜んでいた先輩の作を今も諳んじている。「女教師の主婦である日の初袷」。 教室で読み聞かせすると、自分が惚れ惚れして「これいいわね」。小川未明・新見南吉・浜田広介等叙情的な話を好んだ。そして自分も創作するようになっていた。 書くのは休みの日。取材する場合は長期休みを利用した。本を書いていることで父兄から支持され、得をしたが、先生らしからぬ先生だった。 先生は屡々管理者に陥ってしまうが、吉田さんは違う。言うことを聞くと良いことがあると思わせるよう、物語にして聞かせる。「……したら、駄目」ではない。感動してわかるよう話す。字も書けない子を、話が聞ける子になるまで育てるのが面白い。「それいただきっ!」とこどもの行動や言葉から何か頂こうとアンテナを高くしていた。 こどもと一生懸命取組んでいる時は、不思議と良い作品が書けた。何も抵抗がない時は、暇があっても却って書けないものだ。 |
綺麗なもの  舞台上でも普段でも、お洒落な姿で長い髪を纏め表情豊かに「語る」吉田さん。写真は「懐かしいわね」と処女作を朗読しているところだ。 教え子は「先生は綺麗なものが好きだから」と、綺麗なものをよくくれた。折り紙等手作りの作品だ。低学年の受持ちが多く、荒地に水をまき、肥料をやって種を蒔いていくところに教師の喜びがあった。全員の日記や連絡帳に赤ペンを走らせ、読み聞かせを欠かさなかった。 いつの日もこどもの側に立って書き続けた。 離婚が増えてきた昭和40年代、「七つになったけんちゃん」に取り組んだ。この本で初受賞、受け持ちの一年生の教室で「ほらっ」と賞状を見せたとは、早船さんの談。 この頃「新しいこどもの発見」を提唱した児童文学全盛期の模様は、  「キューポラのある街よいつまでも 早船ちよとなかまたち(平成18年刊)」の中の昭和54年子どもと読書文化夏期講座記録「わたしたちの仕事と、わたしの『峠』六部作について」に辿ることが出来る。 現在取り組んでいるのは猫の物語。沢山の作家を育てた「児童文化の会」が、年1回発行している創作集の原稿だ。 |
読み伝える歳月 退職後、仲間に誘われ「与野朗読の会」に入った。  師・巌金四郎(声・俳優、写真中央。その後が吉田さん)は亡くなったが、年2回、与野の芸術劇場で舞台に立つ。 「語り」を演じては10年。「熊谷の昔ばなしを語る会」では再話をし、図書館や母校・久下小学校で語り続けている。  平成19年くまがや賢治祭 平成19年くまがや賢治祭吉田さんは、こどもと向き合ってきた体験から、今日のこども達を、皆いい子だが、「人間としての核のところがやせていないか」「今の子は本音で人と付き合っていない」という。 そして「こどもとは一人の人間としてとして向き合う」が変わらぬ初心。 師は晩年、「書くことが出来る子なら、自分を客観視出来ているから大丈夫」と書き残した。 新川を舞台にした作品も完成まで後一歩、「平成の民話」も書きたいが、忘れ去られようとしている昔話の再創造も大仕事だ。吉田さんは朝5時半に筆を執れるように努めている。 その切れの良い文体は今日も生き生きとして、凛とした人となりと共に、まさに「文は人なり」であった。 |

 メール |
トップ |
