

contents
| �w13���x�@2008�@7/14 �܂����ʂ�ЂƂтƁ@���̂X �w���Ƃ̎R�֓o��\ �̂����Ă����������� ���{��̌����̎p�x �������w�ҁE�c���v���� �w15���x�@2009�@1/1 �܂����ʂ�ЂƂтƁ@����10 �w�S�ɑ��z���ɗ����āx ���{��ƁE���S������ |

| �܂����ʂ�ЂƂтƁ@���̂X ���Ƃ̎R�֓o��  �������w�ҁE�c���v���� �@�������{�Əo������B �肵�āu��ʂ̂��Ƃi���k�Łj�v �i�������o�ʼn�E�����\�Z�N���j�ł���B �@���̎��T�Ɏ䂫���܂�A �u���v����u��v�܂ňꎚ���ǂB �@�łт䂭���Ƃ����̋��т��������߂āA �\�N���₵���J�삾�B �@��肩����悤�ȕ��́A �u�w�����x�͓��ʂȎg�����v�Ȃǂ̃R���������킢�[���B |
| �@ �̂����Ă��������������{��̌����̎p �@�c����́A����Ɏg���Ȃ��Ȃ�Ǝv���錾�t����肵�A�l�N�O�ɖ�ꖜ��������߂����T�ɂ܂Ƃߏグ���B �@�_�ƁE�{�\�W�̎ʐ^�������B�����̍̏W���S�������E�p���Ƃ�������邽�߂ɕ`��������҂���A���̂�����̂͑}�G�Ƃ��Ďg���Ă���B�g�p�̗L����p��`�F�b�N�͏\�l�Ɉ˗��B�c��ȍ�Ƃł������B �@���T���̓��@�́A�����Ă������邱�Ƃ�ʂ��āA���Ƃ��������₢�����������炾�B���͂������Ďd��������u���i��j���v�̎Љ��Ɏ���Ă������Ƃɂ́A�l�̉��������Ă����Ă����B�����A�Љ�ڂ낢�A�����������Ƃ����ɂ���Ȃ��Ȃ�ƁA�ꗬ����u�S�v�܂ł��������B �@�c�����˂����������̂́A�������`����Ă����͂��̂��Ƃ�m�肽���Ƃ����v���ł���B���Ƃ��W�߂�ɂ́A���ł��������x���B���Ƃ�k��A���̌��͓���A�W�A�����ɂ܂ŒH�蒅�����A���t�̐S���������ւƓ`����B����قǑ�Ȃ��Ƃ��łтĂ��܂��Γ�x�Ɛ����Ԃ�Ȃ��B 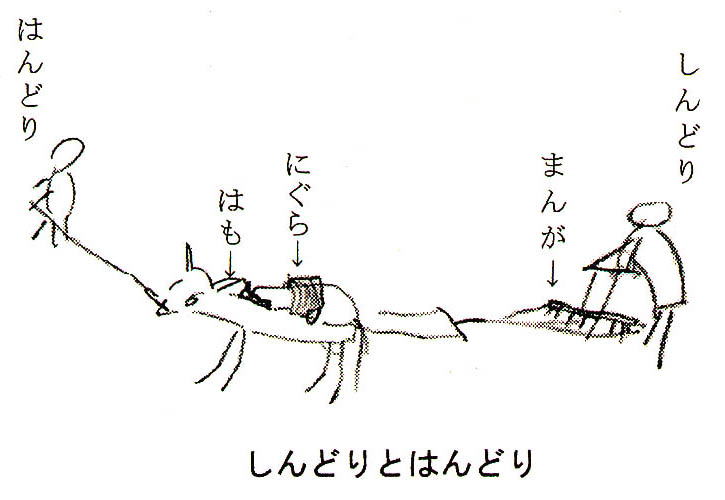 �u����ǂ�v�K��B�n�L���������B���n�̗U�������u�@���i�͂�ǂ�j�v�B�n�L�i�܂j���L�i���j���g�������u����ǂ�v�ł��B �u��ʂ̂��Ƃi���k�Łj�v��� PROFILE �@�������w�ҁE�c���v����́A���a��\�Z�N�A�F�J�s�O���K�ɐ��܂ꂽ�B �@�[�J���ƍ��Z���疾����w���w���i�݁A�|�v���ЂŎ������ҏW�Ɍg�������A�p���E�i���e�[����w�œN�w���w�B �@���a�\�Z�N�A�A����͏o�ŎЂ�L���㗝�X�ɋΖ��B���݂͌F�J�̒n�ŏm�u�t�̖T��A�S���̐Ղ��p���_�Ƃ��c��ł���B �@�����ɂ́A������N�u���u�ƍF��\�Ă�Ƃ����������t�v�A�����ܔN�u��������̖`���v�i���ɂق�Տo�Łj��������B�u���{�q�ǂ��̖{������v�y�сu���{�������w�ҋ���v�̉���B �@����Ȃӂ��Ƀv���t�B�[����H��ƁA���ʂȐl�̂悤�����A�u�D���Ȏ�������Ă��邾���B���̐����X�^�C�������ꂼ�ꂪ�ǂ��C���]���Ȃ�ł��v�Ǝ����Ȃ��Ɍ��ɂ���B �@���̎��R�̂���́A�L���ȕ��y�̉��A�c����ɂ˂�˂����Z�ŕ��Ԃ��Ĉ炿�A�����Ƃ��������Ɍ��������Ă��������M����B ���������̕��� �@���̓��A�c�Ƃ̕ꉮ��K�˂�ƁA���ꂳ��������Đ̘b�Ɏ���Y�ꂽ�B�u�œ���̎��̌��g���܂������v�ƁA�ǂ����ւ炵���ȕ�̔��コ��B���v����̏��N������A�u�Վ��̉ł͖Z�����ĂˁA�q�ǂ��Ȃ\���Ă����Ȃ��B��`���𗊂ނ������āA�_�Ƃ̎d���ʼnƂɂ��₵�Ȃ��B���Z���̍��ɂ͍��~�Œ�Ɩ����ɖ����ɂȂ��Ă�����v�ƕ�����Ă��ꂽ�B �@����Șb���f�����̂́A���ĖS���Ȃ�����������̏��ւ��B���̏�ɁA���R�ƌ̐l�̃p�\�R���⏑�ރt�@�C��������ł���B �@�p��́A��͓����������A�x���܂œǏ������B�^�ʖڂœ����ҁA���ł����Ȃ����B��O�͕����̓����̕ĉ��Ŋw�Z�ɒʂ��A�ʐM�m�̎��i��������Ƃ����B �@���̕��e�Ɏ���ꂽ���Ƃ�����B�܂��q���̎����A�Z��Ő��~�������̂��Ƃ��B�u��x�Ƃ��܂���v�Ƒf���Ɏӂ����B �@���U�̃e�[�}�ɏo������̂́A���Z���ゾ�����B���ꂪ�N�w�ł���B�u�l��������Ƃ������Ɓv��ǂ����߁A�u�P�̌����v�̐��c�N�w�ɍs�������B�T�䏟��Y�A�e�a�c�c�Ђ�����{��ǂB�m�[�g�͐ςݏグ��ƎO�\�Z���`�ɂ��Ȃ����B �@�₪�Ď��\�N��A��w�͊w�������Ń��b�N�A�E�g���ꂽ�B���Ƃ��Ȃ�����A���Ԃ͂���]��قǂ���B���⏬�����������B�o�C�g�オ���܂�A�����@�ƃJ�����o�b�N��w���q�ł����ŁA��l�R�֓o�����B�~�͖k�C������Q�����B���I�����ƌĂꂽ��҂������b�N��w�ɊO�֊O�ւƕ����o�����x�������������B �t�����X�� �@���ƌ�A�������đn�Ǝ҂��F�J�o�g�ł���u�|�v���Ёv�ɏA�E���邪�A��\�Z�ɂ��ēn�������f����B�w�x���O�\���x���w�Ԃ��߂��������A�\�z�O�̓]�@���}����c����ɐe�͑唽�B�����A�u�d���Ȃ��ł���ˁB���������₢������܂�������v�B�c����͎����̎v����D�悳�����B �u���܂Ƀt�����X����d�b���|�����Ă��Ă��A���b���Ă������킩��Ȃ��Ă˂��v�ƁA���コ��͓�����U��Ԃ����B �@�t�����X�������D���Ńt�����X���������B����ł��A�ŏ��̈�N�͒P�ʂ�S�����Ƃ����Ƃ����B�A����̓t�����X�̗F�l�����N�������Ƃ��������B�u�t�����X�l�͗��_�D���Ŏ��䂪�����Ƃ悭�����邪�A����Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B�����A���A�l�݂͂ȓ����ł��v�ƁA�c����͘b���B �@�ق��đ��q�̂��Ƃ�����葱�������e���f���炵�����A��Ƒ��ň�����l�́A�ǂ��������傫���B���S����A���ǂ͈₳�ꂽ�_������ȕ�Ƃ��āA���悤���܂˂œc������葱���Ă���c���B �@ �@�b�̓r���A�V�тɗ������삳��Ƃ���������o�����B��̖P�M�N�͐l�������A������ƈ��A���Ă����B�c����͎������g���u��i�����j�v�ƌĂB�v���Ή����Ȃ��Ƃ��B �@�����̖���₦�A�����́A�u�܂䂱�v�c�c��������Ȃ�A�{�\�̐���ȓ��n�ł́A���������ɂȂ�\�́u���\�i���j���܁v�Ƒ�ɂ��ꂽ�B���̎����Ɗm�F�������A������ƔP���Đ^�D�q����ł������B �u���u�ƍF��v�Ɓu��������̖`���v �@�c�����̐��U���т��A�����܂ł�����葱�����u���̓N�w�v�B����ɂ͏\�l�ŖS���Ȃ������Ƃ��̑��݂��傫���B�Z��̂悤�Ɉ�������Ƃ��͔]��ᇂ������B���������Ă��������Ȃ������B���̎������w�̓��i�́A�v�t���̏��N�̎����֎�����݂��ׂ₩�ɕ`���ꂽ���̂����A�ǂ���ɂ��c�����𗎂Ƃ����N���o�ꂷ��B  �@�c����́u�ߒ��v����Ȃ̂��Ƌ����Ă��ꂽ�B�͕ω����Ă���B�ω��̒��ł��̂�����Ƃ������ƁB�����āu���f�v����ԑ厖�Ȃ̂��B�u���v�Ƃ����̂́A�u�o��ł��邩�ۂ��v�Ƃ������ƂŁA���������~����Ƃ������Ƃł͂Ȃ��B�����邱�Ƃ͉�����T���Ă��邱�Ƃł���B �@������������A�u�͂ޕK�v�͂Ȃ��̂�������Ȃ��v�B �@������A�c����́u���ʁv�����A������o�傪��܂�O�̍��ׂ����������Ǝv���B�u�ߒ��v���D��������B �@�u���u�ƍF��v�ɂ͇��F�J������Շ����ω��R����_���̕�炵���������܂ꂽ�B �@�u��������̖`���v�ł́A�n���̇��������܇����K���������r�쇁���厖�ȏ�ʂɓo�ꂷ��B���̏I�͂ł́A���̎������o�q�̒킪�Z��肩����B �w�c�c��߂̎₵���ɑς���͂ď��߂āA�����̐��⎩���ȊO�̐l�̐����������邱�Ƃ��ł���̂��B�����̂��Ƃ���l���Ă�����A�����~���s���ɂȂ�B��������邱�Ƃ��Ȃ�����ˁB�����ǁA�����Ă��邱�Ƃ̑������������A���l�̍K�����F���悤�ɂȂ�ƁA���̊Ԃɂ��������~���Ă�����̂��B���ꂪ�����邱�Ƃ̏o���_�Ȃ̂��Ǝv���B���܂��������̏o���_�ɗ��Ă邩�A���ꂪ���Ă��Ă��B�ς��Đ����Ă����B�N��B����̕��܂ŁB�c�c�x ���ǂ������� �@����A���ǂ��̐�ΐ������Ȃ��B�������ς��A����Ȃ��ǂ�����̂������B������S�g�̌o�������Ȃ��̂��B�m�ɒʂ����ǂ��ł��A���͂Ŋw�ԂƂ������Ƃ��ł��Ȃ��B�ǂ���w�֍s�����Ƃ��Ă��悪�����Ȃ�������̈ӗ~���Ȃ��A�u�������낳�v��m��Ȃ��B�_����邱�Ƃ����l���Ȃ��B�{���u�I�^�N�v�͖J�ߌ��t�����A�ᔻ����Ă��܂��B�������A�u�w�͂��Ă��d���Ȃ��v�̂ł͂Ȃ��B�����ʂ��o�Ȃ��Ă��A�����A�K���������������ԁB���̓��Ɍ������ĕ����ė~�����B �@�����邱�Ƃɐ^�������Ɍ����������Ƃ̑f���炵�����A�����邱�ǂ��B�ɓ͂������B ���ɂ�  �@�L�X�ƕ������n�鐰�ꂽ���j�̒����B���Ɣ_�Ƃɂ͐�D�̂����a�A�ӂ�ł͖Z�������ɔ�����Ɠc�A���Ƃ��s���Ă���B��E���コ��́u���n�߂������肾��B����ȓ��͑����Q������̂Ɂv�B  �@���̓��̍�Ƃ̓R���o�C���Ŋ����������g���N�^�[�ň����ב�̏�̑܂ɐς߂ăJ���g���[�G���x�[�^�[�܂ʼn^�Ԃ̂��Ƃ����B���̌J��Ԃ����B�R���o�C���𑀍삷��c����͒����A�X�q�Ƀ}�X�N�Ɗ��S�h�����B�r�C�ʂ������B���œ|�ꂽ����������d���グ�Ċ�����A�������ɂ��Ē��ɒ��ߍ��ނƂ����}�W�b�N�Ɍ��Ƃꂽ�B �u�̂͊��Ŋ�������v�Ƃ������コ��B�ォ�����ė������l�̍K�b������m�𑩂˂Ă���B���̌�k���Ă���엿�����A����A��~�����Ă���A����Ɠc�A���ƂȂ�B�z�̉��ł��ꂱ��������Ă��ꂽ�c����B�u�_�v�̂������낳�Ɉ������܂ꂽ�B �@�c����́A���u��x�v�ɒ��肵�Ă���B�����͑�̑������B���̐��_�I�����܂ł�`���肽���Ƃ����B�u�l�͎��ӂ���U�߂čs����ł��B�R�̒���ɂ͂Ȃ��Ȃ����ǂ���Ȃ����A���ꂪ�y�����v�ƁA�ꂢ���B |

| �܂����ʂ�ЂƂтƁ@����10 �w�S�ɑ��z���ɗ����āx  ���{��ƁE���S������ 1920�@�����S�g�c���ɐ��܂�� 1937�@��[��w�Z�m�敔�Ɋw�� 1947�@���G������{��ɓ]�� 1948�@�t�̉@�W�E��33��@�W�ɏ����I�B�Ȍ��ܑ��� 2001 ���{���p�@���l�ƂȂ� 2008�u���v��93��@�W�ɂāu�����Ȋw��b��܁v |
�@�@������\�N�㌎�\�l���A�A�x�̓��킢�̒��A���̓m�́u�����s�����p�فv�֓��������B�J�ْ���̑������ԁA�܂��搶�͂��炵�Ă��Ȃ����낤�Ǝv���Ȃ���@�W�̃R�[�i�[�ɕ��݂�i�߂āA�ӂ��ƌ�������ƁA�l�_��D���ċ߂Â��Ă���̂́A�����̃X�[�c�ɖX�q�A������������������Ƃ����p�̑��S�����B���̓��͓��ԂŎ�t���T�����ɋl�߂�̂��Ƃ����B�Ď��̔N�ɁA�����Ȋw��b�܂���Ƃ̖ڂ́A�������D����ῂ����B �@���̎��A�����x�ڂ̉@�W��i�Q���������B���{��Ƃ����Ă�����ɂ����Ă͑��l�ȉ�@�E��肪����A��Ƃ��i�����m�������l�X�ȍ앗���ꖇ�̊G�̒��ɍ����Ă���B����Ȓ��ő�여�u�@��ʂ�`�@�v�́A��͂�B�ꖳ�B  �@����̎�܍�i�u���v�́A�����E���E���F�Ɣ����ȃO���f�[�V�����̒��j�̂Ƃ���ɁA���������݂̂�����B��d�ɂ���芪�����̗ւ́A����������g�̂悤�ɕY������A���̒���ɕ����Ԍ������E�̐^�ł���Ɠ����ɁA�l�̖��̎W�߂��ɋ��������A�܂��z���Ă����Ƃ����ɂ��邱�ƂŁA����҂𗣂��Ȃ��B�Ŗ�ɉi���̕��������A�����̌����y���Q�������B |
| �@��i���E�̗h�邬�Ȃ��͌v�Z���ꂽ�F�̍\�z�ɂ���Ă��āA������x���Ă���̂��u�@��ʂ�`�@�v�Ȃ̂��낤�B���엲�i����ʋߑ���p�يw�|�����j�͂����B�u����͔����Ȕ������������Ĕ���������ׂȐF�_���k���ɏd�˂Ȃ���t�H�������`�����A�h��c���ꂽ�n�̕���������ΐ��𐬂��Ƃ�����ϕ��G�ȋZ�@�����A���̌��ʂ͂��Ȃ��牐�₩�ȐD���̂悤�ɔ������~���������炷�v �w���؋��n�ƕS���N�L�O���S�����{��W��i�W�x�i������N�j 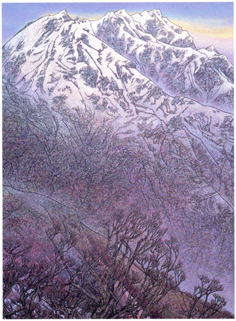 �u�J��x�v���a61�N�@���{���p�@�܁E��Ϗ� |
| �@���̓���������̔��p�t�@���ɉ����鍇�ԁA��삳��͉��̈֎q�ɍ��𗎂������Ă����b���ĉ��������B �@�c�c�����G�ɖڊo�߂��̂́A�w�Z�֏オ��O�̂��Ƃł��B���̊ŕa�������q�̎��̖�ڂł����B�c�����͂��̖����ŊG��`���ėV�сA���̖��ւ��Ԃ߂܂��B�����������q�ɂ���Șb�����ĊG��������ƁA�q�ǂ��̎��Ƃė_�߂ĉ�����B���ꂪ�������Ċ������āA�G���D���ɂȂ�܂����B�w��]�S������Ώ��ɂł���悤�ɂȂ�Ƃ������Ƃ́A�����g�������ċ����Ă��ꂽ���Ƃł��B �@�c�c�����S���Ȃ荂�����w�Z���I����ƁA��������̐}�ĕ`���ɕ���ɏo����܂����B�ł��A�[���ē�N�ŋA���B���͐e�ʂɊG�`���������Ƃ��B�����͉�ƂȂǗ�������܂���B���̉Ƃ����ƕ���͏o�������Ȃ��Ɣ�����܂������A�S�Ɋ�������̂�����A���̈�N����ɂ͏㋞�B�\���̎��ł����B��͒��ő�������点�A�u���ꂩ��A�ǂ��łǂ������悤�Ɛ����ɐ����Ȃ����v���������āA����o���Ă��ꂽ�B �@�c�c�����͋ꂵ�������ł��B��\��̎��̂��Ƃł����B�������p�w�Z�œ����Ă��������A���m���p�j�̊��q�F���Y�搶���������̑��ӂɌĂт܂����B���͌����ɕ����Ă����₵���Â�������Ă����̂ł��傤�B�搶�̌��t�͂����ł����B �u���̔��i�n�[�j�̖̌��̂��̗[�z�����Ȃ����v �@����ƁA�^���Ԃɍg�t�����Ɨ[�z������܂����B �u���̖��邭�傫�ȁA�������������z�̐S�����̂��S�ɂ��邱�Ƃł��v �@���̓����玄�͕ς��܂����B���̌��t��l�ԂƂ��Ă̐S�̎x���ɂ��Ă��܂��B �@�c�c���z�߂܂��B���Ƃ��J�ł��܂�ł��A���̏�ɂ͕K�����z������܂��B�ǂ�Ȃɋꂵ�������傫�ȐS�ł��悤�B�����v���ĕ`���Ă��鎄�ł��B���̎���A���q�搶�ɗǂ��S�������Ă����������B�����č��A�ɐɌڂ݂邱�Ƃ́A�S���炻�̂悤�Ɏ������M���A��������s�������ۂ��Ƃ������ƂȂ̂ł��B�ǂ�ȂɎ₵���������̌��t�������āA���̎�������܂��B �@�c�c���̌��̊G�̎ʐ��͐X���̊�؎R�ɏo���������̂��Ƃł��B���̔����������˂���ďh�����A�^�钆�ɓƂ��ޓ���������ĊO�֏o���B�ӂ�͐Q�Â܂��āA�N���Ă���͎̂������B�������Ă��邾�낤���B�R�̒������������ƒ��H�̖����Ƃ�������̗؉_�B�ƂĂ��ǂ��C�����ł��B�Ƃ萟��C�̓��k�̎R���Ō��ƌ��������A���M�ʼn��������Ă���F�����܂��B�~���Ɛ�������̂ł��̍��͐F���M�ł��B�����͍̂D���ł�����S����ɂȂ�܂���B  �w���؋��n�ƕS���N�L�O���S�����{��W��i�W�x�i������N�j �@�c�c�V�R�̐��E�ɓ���A�u���肪�Ƃ��B���肪�Ƃ��B���ɂ��Ȃ���`�����ĉ������v�ƔO���܂��B���������̂ɏo��ƁA�����ɂȂ�̂��l�Ԃł��B�u���Ȃ��̔����������ɉ������v �@�����Ŕ���������B���ꂪ�ʐ��ł��B�厖�Ȃ͓̂Ƃ�Ō��������Ƃł��B�ǓƊ����Ȃ��Ƃ��߂ł��B |
| �@�������đ�삳��͂����g�ł��A����Ȃӂ��ɏ�����Ă���B �t�����y���ƊG�̓�(����) �w���G�����N�قNJw�ѓ��{��ɓ]�����A��ɕ��i��`���ĉ@�W�ɏo�i�����B���ɓ~�i�F�ɐS���Ђ���ʐ��ɂ͎O�����l����̏����ȃX�P�b�`�u�b�N�ƎO�\�Z�F�̐F���M�������ďo�������B �@���̃X�P�b�`�������搶�Ɍ��đՂ����B�������߂���Ȃ���A�F�ʂ����ꂢ�ɂł��Ă���˂ƌ���ꂽ�B�����u�搶�̓X�P�b�`�̒��F�͉��ł���܂����v�Ɛq�˂��B�搶�́u�F���M�̂��Ƃ������A���ݕS�F�߂��F���M��p���Ă���v�B���̐F���M�͂ǂ��Ŕ����Ă���̂ł����Ɛq�˂�Ɓc�c�t�����X�̐��i�Ő_�c�̕��[���Ŕ����Ă���Ƃ̂��Ɓc�c�u�~�v�A�����̓~�͑�ςȂ��Ƃł��B����ł��A�z�V�N�e�A�z�V�N�e�A������ߖ�ɂ���N�����Ƃ��̐F���M�����Ƃ��ł����B �@�������Ď��̐F���M�̎ʐ������悢��{�i�����A�F�ʂ�������������Ɖ��M�̐��̊Ԃɒ��F����悤�ɓw�͂����B���̃X�P�b�`�̕`�@���{��ɗp�����āu�@��ʂ�v�`�@�ƂȂ����B�ׂ₩�ȋC�Â����ƍ��C�̂���`�@�Ȃ̂ŁA���ɂ��l�����Ȃ��B�悵����ňꐶ����ʂ��̂��B�T�����Ɣ������G�ł͂Ȃ����A�S�Ƀq�b�J�J���G��`�������A��킭�Ό��ĉ�����l�X�̐S�ɂƂǂ܂�G��`�������c�c�B �@���ꂩ����N���߂������A�܂������y���搶�ɑ�ςȋ����������������B �@������̂��Ƃł��B���̎ʐ�����������Ă���A���ڊԂ̃e�[�u���̏�ɂ��������p�}�b�`�̖_���܂݁A�e�[�u���̏�Ƀp���p���Ɛ���܂���A���ꂭ�炢�Ȃ�{������������ˁc�c�����đS�����܂���āA����Ȃɂ�������Ɛ������Ȃ��B��삳��͕`���ĕ`���Đ������Ȃ��قǕ`���ƁA�����Ɏ������\����������Ȃ��̂��łĂ���B�܂�u�S�������Ĉ��\���v�B���́u��������ĕS��\�������v�Ɗ���ēw�͂��Ă���ƌ���ꂽ�B�t�͂��肪�����B �@�t�̂��Ƃ� �u�G�͎�ŕ`�����̂ł͂Ȃ��A�S�ŕ`�����́v�����āu�i�i�̍����G�A����͋C�i�ł��ˁB�l�i�ł��ˁv�ƌ���ꂽ�B�x  ������\�N�㌎�\�l�����̓m�u�����s�����p�فv |
| �F�J�ɂ���� �@��삳��̑�삳�鏊�Ȃ́A���̓Ă����y�����B�A�g���G���Ă��炸�A�킪���̗l�X�ȕ��������̒��S�ɂȂ��čs�����Ă����B �@�����I�߂��́A�w�F�J�s���p�W�x�����̑O�i�K���甭�Ă��A���玖�����߂Ĉ�ďグ����삳��́A�F�J�s���}���ق�w�r���ɂ��������s���M�������[�̊J�فE�^�c�ɂ���^�����B �@���a�O�\�N���A�u�������v�������������A���̌����Ɍ��������o�Ȃ��A�O�\�N�ԍu�t�߂��B���̉�͔��؋��{���Y�A�����ɒ���H��i���F�J�s�����A����j�Ƃ�����Ԃ�ŁA��ɂ́u���̉�͊G��̍D���ȁA����������Ȏғ��u�����ɂ𗘗p���ĊG�M���Ƃ�A���킽�����������̒��Ɍ|�p�I�ȂЂƂƂ����������A���邨���̂���y�����l���̂ЂƂ��܂Ƃ��悤�Ƃ���̂ł��v�Ƃ���B �w��ʌ����p�W�x�ɂ͌\�Z��A���o�i�B�w���k���p�W����x�̐ݗ��ɐs�͂����̂́A���a�O�\�O�N�̂��Ƃ��B���a�l�\��N�ɂ́w���k���p�Ƌ���x��n���A�O�\���N���L�O���ĊJ�Â��ꂽ�w���k�Ŋ����|�p�Ƃ����x�W�ł͋L�O�W���s�ψ����߂Ă���B �@�܂��A��Ƃ́u���܂��⌫���̉�v���Ăт��������N�l�ŁA�ږ�߂Ă���B���ɐS���ČF�J�������K�˕����ʐ����d�ˁA�w�����l�T���X�^���x�ɂ��ւ����̊G�t���𐧍�B�����k���A�������̕ی�ɂ��S���ӂ����B �@�擹���\�N�A�����ČF�J�ɍ��������̘Z�\�N�̕��݂͑����B |

 ���[�� |
�g�b�v |
